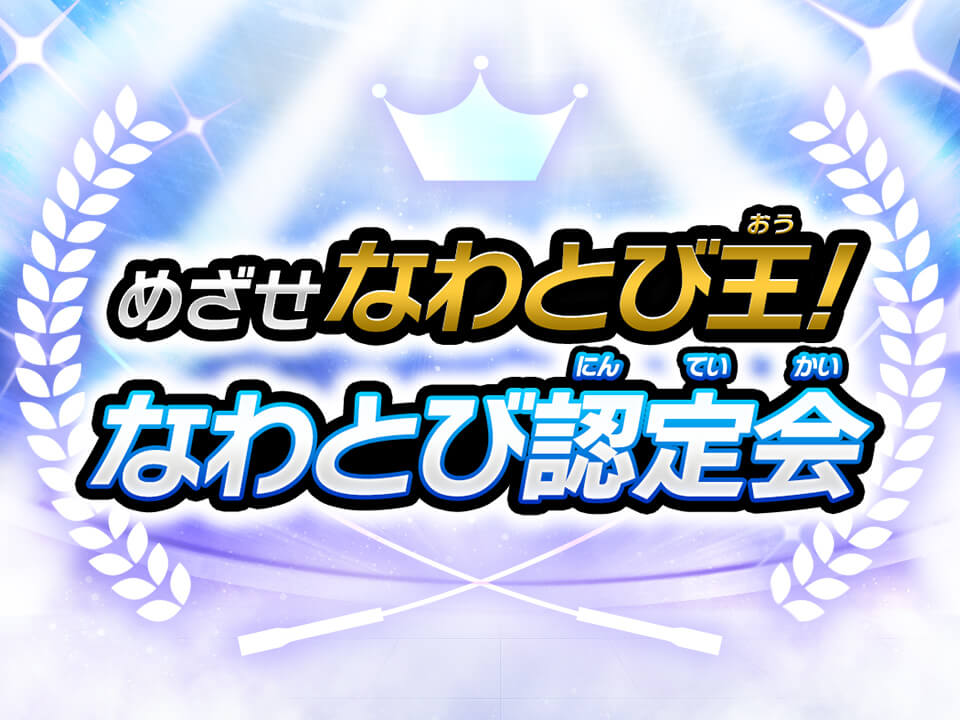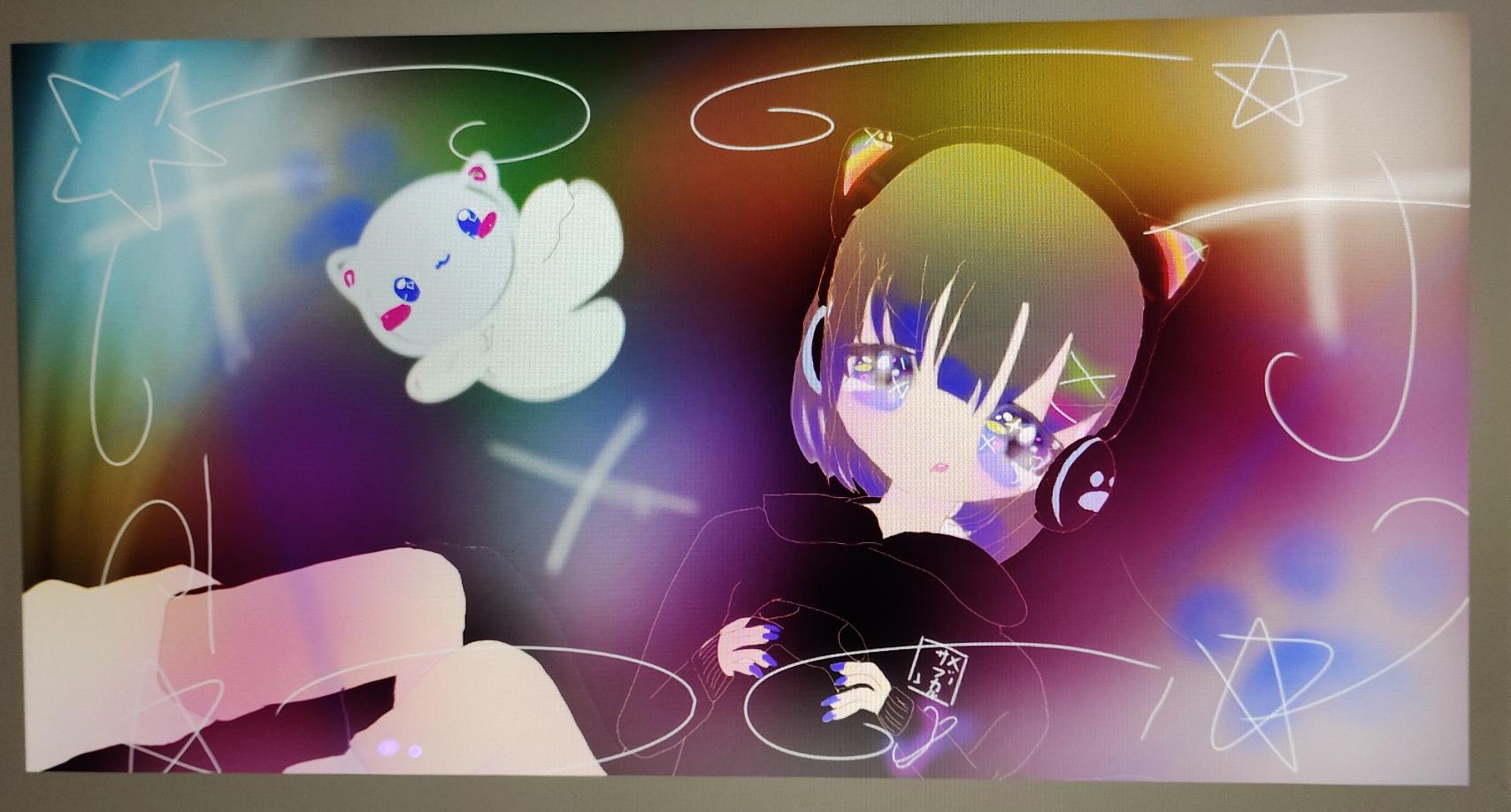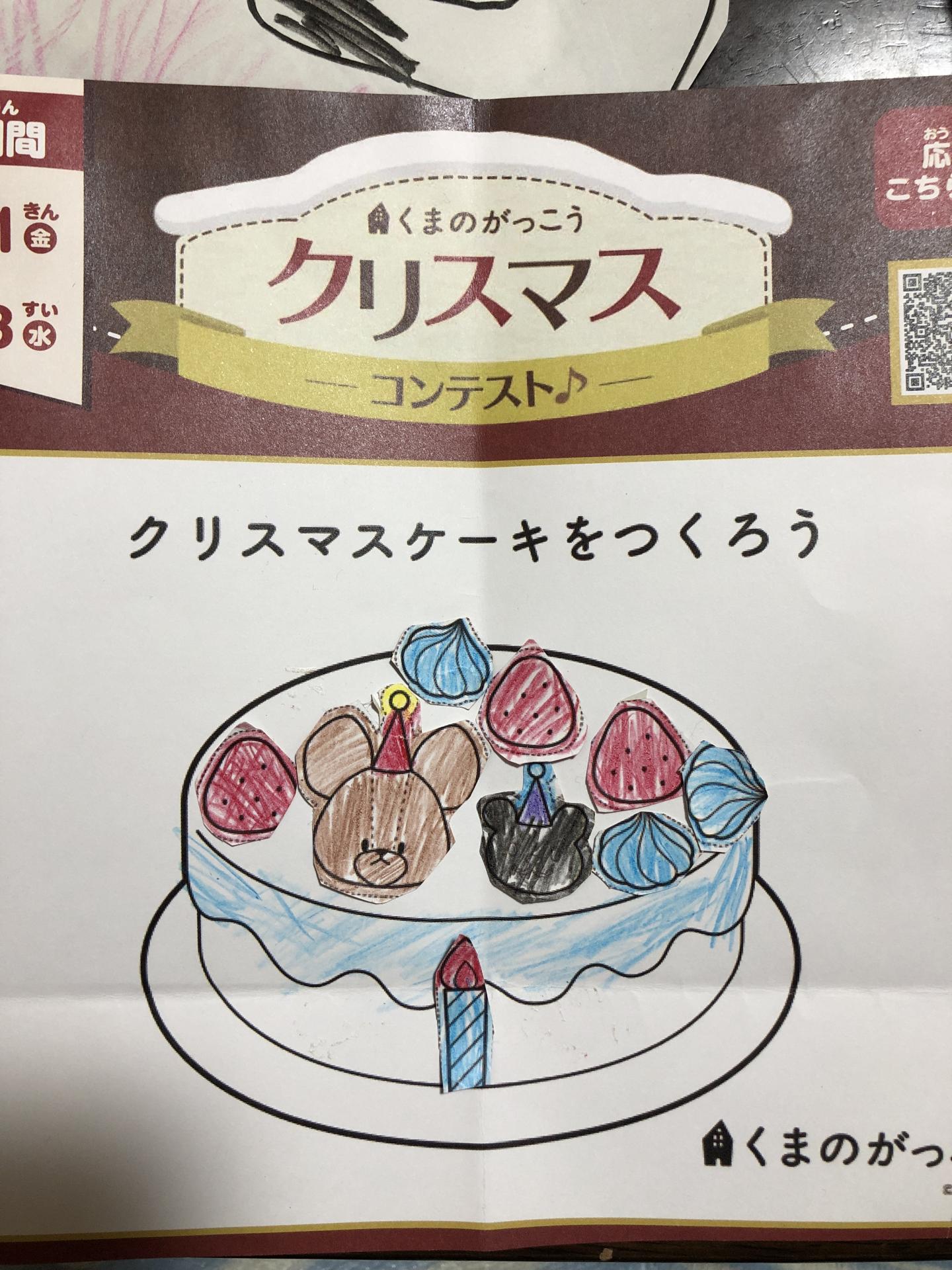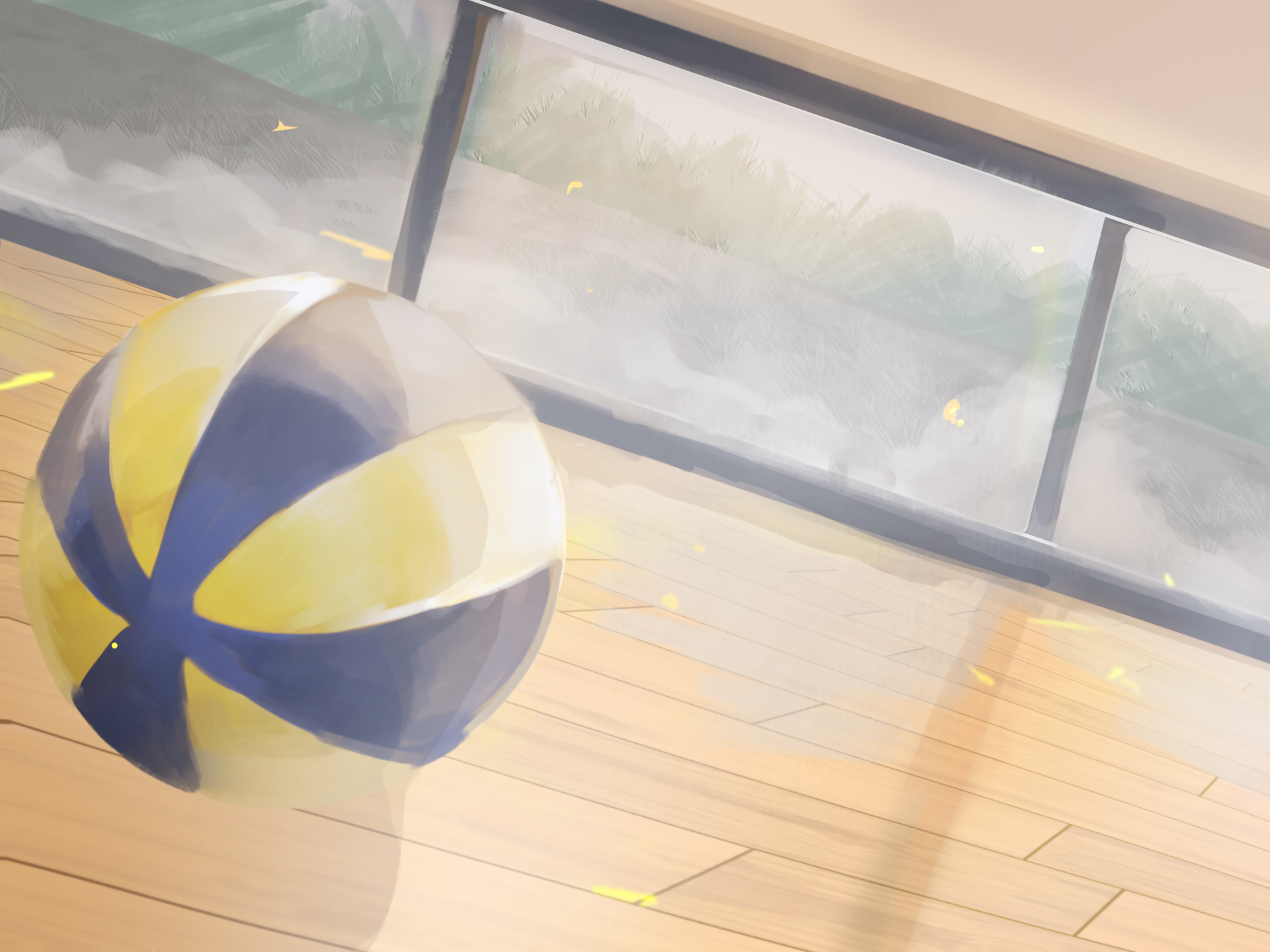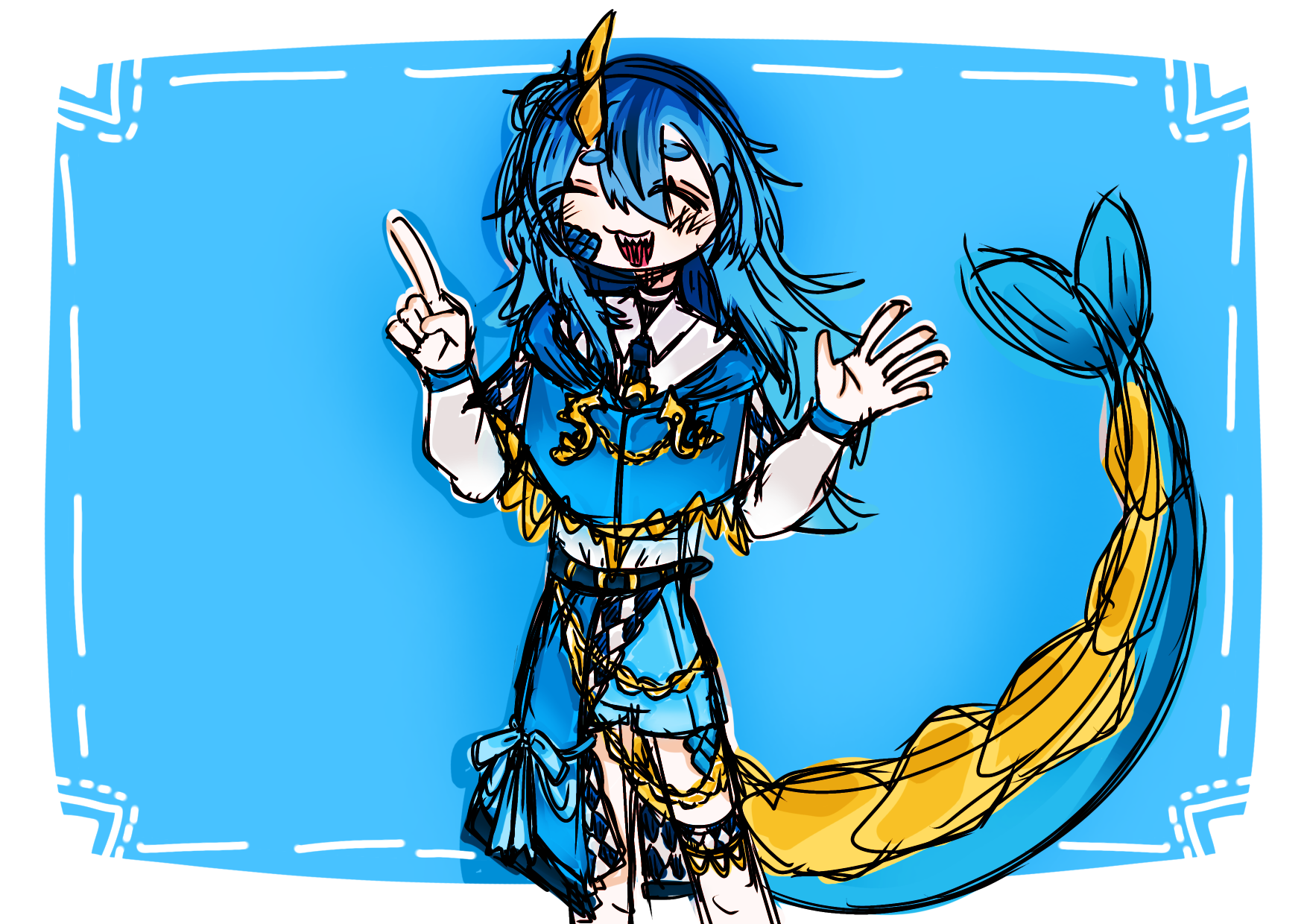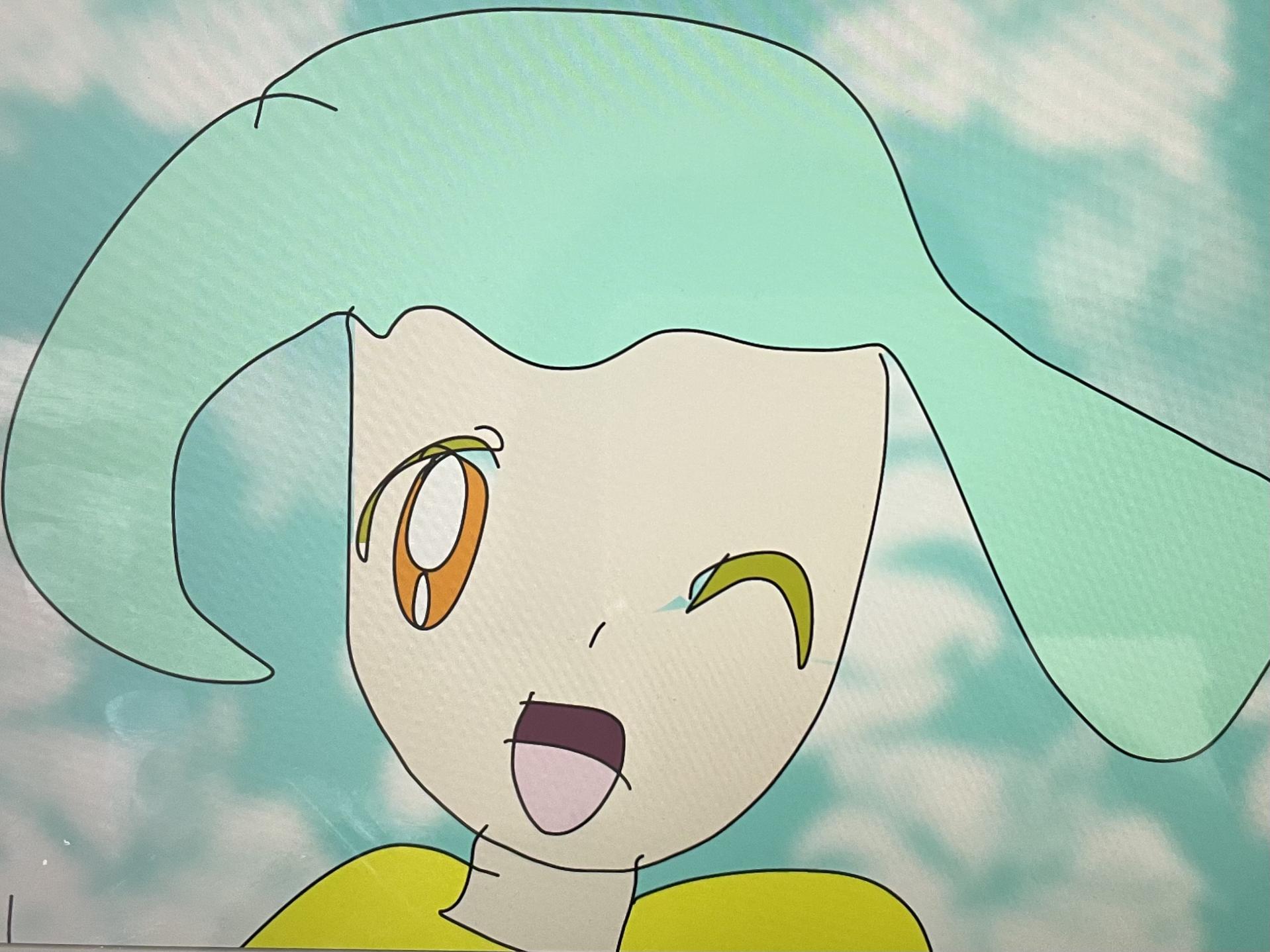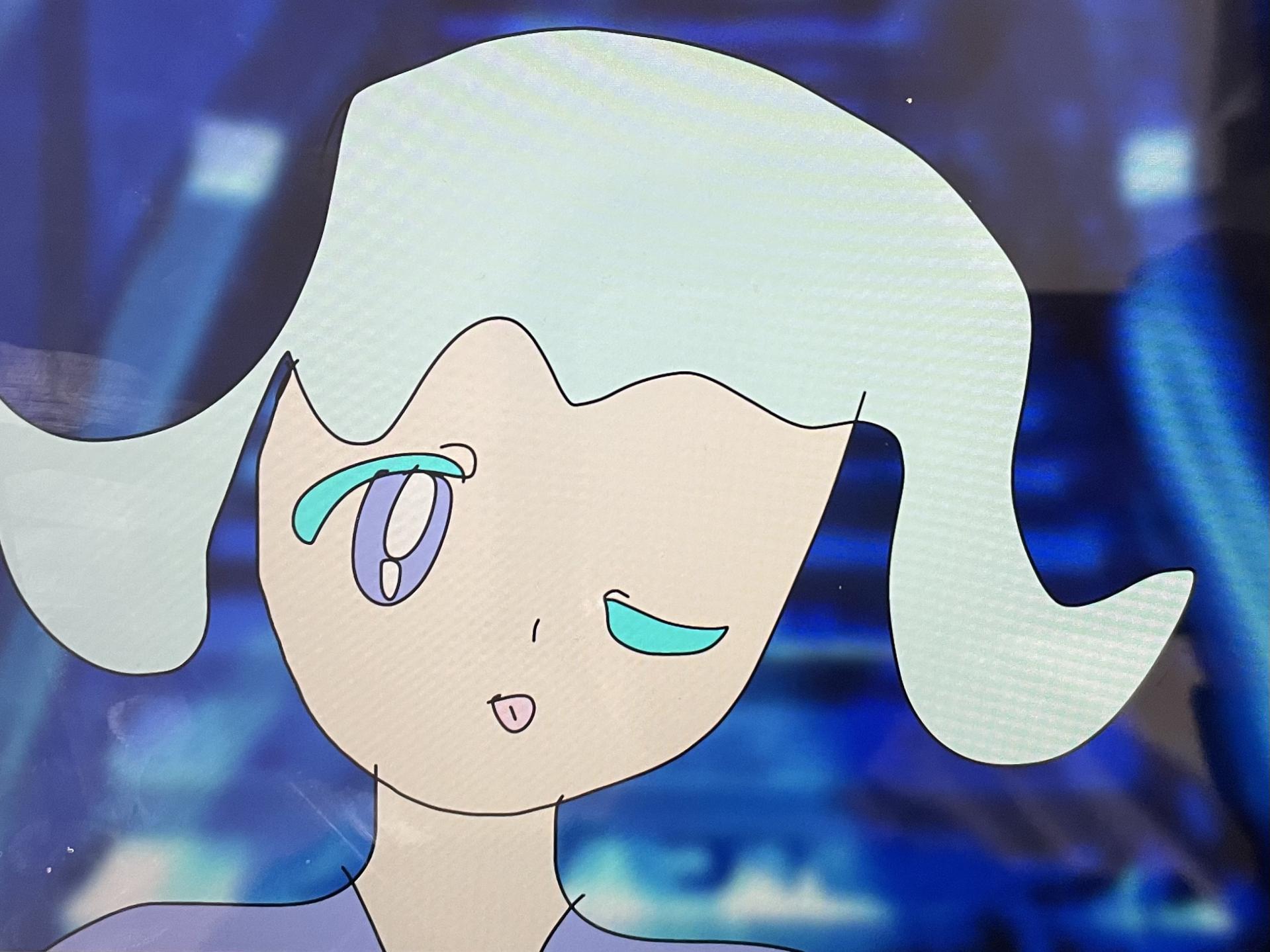私たちの生活に欠かせないお金ですが、その成り立ちや国ごとの違いについて考えてみたことはありますか?現在では、インターネットを使って外国のお店で物を買えますし、外国から日本に観光に来たお客さんも不便を感じることが少ない仕組みが整備されています。この記事では、世界のいろいろなお金について紹介しながら、国をまたいだお金の仕組みについて解説します。
この記事をいいねと思ったらクリック!
この記事のもくじ
【国別】お金の種類と通貨記号

日本で使われているのは、「円」(\)ですが、この円は日本だけで使われていて、他の国では別のお金が使われています。お金にはたくさんの種類がありますが、ここでは特に有名なものを紹介します。
アメリカで使われているドル($)
世界のお金の中で最も有名なものが、アメリカで使われているアメリカドル(米ドル)です。実は、ドルという名前のお金を使っている国は他にもあり、カナダドルやオーストラリアドルも存在しますが、一般的に、単に「ドル」という時はアメリカドルの事を指します。
アメリカでは「セント」も使われていて、100セントで1ドルの価値があります。主な硬貨には、1セント、5セント、10セント、25セントがあり、亜鉛、銅、ニッケルなどの金属を混ぜたもので作られています。1ドル以上は紙幣で、1、5、10、20、50、100ドルの6種類のお札が使われています。それぞれのお金には、アメリカの建国やその後の成長に大きな貢献をした政治家達が描かれています。
ヨーロッパの共通通貨ユーロ(€)
ヨーロッパの多くの国で使われているお金はユーロです。ユーロは比較的新しいお金で、一般に流通し始めたのは20年ほど前です。それでも、アメリカドルに次いで大きな規模を持っている重要なお金です。
多くの国で使われるユーロ紙幣のデザインには、政治家や王様のような特定の人物ではなく、ヨーロッパの歴史上の建築様式を備えた一般的な建築物が描かれています。ヨーロッパには戦争などの暗い歴史もたくさんあるので、多くの国の人が嫌な気持ちにならずに使えることは重要ですね。
一方で、ユーロ硬貨では、片面が共通デザインで、もう片面は硬貨を発行する国が自由にデザインできるという面白い特徴があります。国ごとに片面のデザインが違いますが、ユーロを使用する国であれば、どの硬貨も同じように使用できます。これらの硬貨には、鋼(鉄に炭素を少量混ぜたもの)や銅、ニッケルなどの合金が使われています。
イギリスで使われているポンド(£)
ポンドは、イギリスやエジプトなどで使われているお金の名前ですが、一般的に「ポンド」と言えば、イギリスのポンド(スターリング・ポンド、英ポンド)のことを指します。ポンドには古い歴史があり、アメリカが成長する以前には世界のお金の中心的な役割を担っていました。
イギリスのポンド紙幣に描かれているのは、イギリスの偉大な政治家、芸術家、科学者などです。1ポンドは100ペンスと交換でき、イギリスでは1ペンスから2ポンドまでの8種類の硬貨が流通しています。これらの硬貨にも銅や、鉄、ニッケルが材料として使われています。多くの人が日常的に使う硬貨には、価格や耐久性、安全性の理由でこれらの金属が使われることが多いようです。
お金の記号の由来

円は\という記号で表されますが、これは円のアルファベット表記「yen」の頭文字Yに由来していると言われています。他のお金の記号には、どのような由来があるのでしょうか?
ドルの記号の由来
アメリカドルと記号は$で、アルファベットのSに縦線が1本入ったような形状をしています。この記号の由来は諸説ありますが、昔のアメリカ大陸で強い影響力を持っていたスペインの通貨「ペソ」をPSと書く習慣が変化して、PとSを重ねて書くようになったことが現在の$記号につながったという説などが知られています。
ユーロの記号の由来
ユーロの記号€の由来になったのは、ヨーロッパをアルファベットで表した時の頭文字Eです。€はEに横棒を1本追加した形をしていますが、この追加された横棒はヨーロッパの安定性を意味しているそうです。戦争の歴史を乗り越えて、平和で安定したヨーロッパへの願いが反映されています。
ポンドの記号の由来
ポンドの記号£の元になったのは、ラテン語で天秤を表す「Libra」の頭文字Lです。古代ローマ時代から使われている重さの単位に由来し、長い歴史的な背景が推測できます。
ニュースでよく見る「為替相場」とは?

今では、日本から海外のお店に注文をしたり、外国の会社にお金を払ってサービスを受けたりすることが簡単にできる仕組みが整備されています。この背景には、各国のお金を交換できる場所(為替市場)の存在があります。
お金の価値は国ごとに違う
現在では、多くの場合、国ごとのお金の価値は日々変動しています。これは、為替市場でお金を交換する時の比率(為替相場、為替レート)が日々変わっているからです。為替相場は、1ドルを何円と交換できるか、といった形で表現されます。ある日には、1ドルと100円を交換できたのに、別の日には130円も必要なんてこともあります。
1ドルと交換するのに必要な円の量が少なくなることは、(ドルに対して)1円当たりの価値が高くなっていると言えます。反対に、ドルの価値は(円に対して)低くなっています。
円安・円高の仕組みについて
円の価値が下がることを「円安」(えんやす)、円の価値が高くなることを「円高」(えんだか)と呼びます。円高や円安が起こる原因は、お金を持っている人がどの通貨を欲しがるか、人気と密接に関係しています。例えば、多くの人が日本円を欲しがる場合には、日本円と交換するために外国のお金がたくさん必要になり、円高になります。
どの国のお金を持っていることが有利なのかは、非常に複雑な問題です。分かりやすい理由の一つは、銀行にお金を預けた時に受け取れる利息の違いです。例えば、日本の銀行に円を預けた時は1年ごとに預けた金額の1%を受け取れる時に、アメリカの銀行にドルを預けたら1年ごとに2%の金額が受け取れるとしたらどうでしょうか?円をドルに交換して、アメリカの銀行に預けた方が得な気がしますよね?多くの人がそのように考えると、円の人気が下がって円安に進みやすくなります。
日本が外国のお金を作ることもある!

世の中には、偽のお金を作ろうとする悪い人が後を絶ちません。そこで、世界中の国々は偽物のお金と見分けられる仕組みを硬貨や紙幣に盛り込んでいます。残念ながら、悪い人達もその仕組みを見破ろうとするので、常に最先端の技術を取り入れる必要があります。日本では「造幣局」が通貨の製造を担当していて、世界的にも高い技術力を誇っています。
日本で作られた外国通貨の例
実は、日本の技術を使って外国の通貨を作ることもあります。これまでの例の多くは、日本と外国の友好関係を記念して特別に製造される記念コインの製造を造幣局が担当したものです。
件数は少ないですが、造幣局がバングラデシュとジョージアという国で一般的に流通している硬貨を製造したこともあります。これらの国に行けば、日本で作られた硬貨と出会うこともあるかもしれませんね。
外国と日本でお金の使い方に違いはある?

生活と密接に関わるお金の使い方には、各国の特徴がよく現れます。特に注目されているのは、現金とキャッシュレス(現金以外の方法でお金を払う仕組み)のどちらを好むか、という違いです。
日本人は現金が好き?
日本人は、国際的にみて現金を使う比率が比較的高いと言われてきました。クレジットカードや電子マネーは多くの人が持っているにもかかわらず、現金での支払いも一般的です。日本は治安が良いので、偽札などの心配が少なく、現金を持ち歩くことに対する抵抗が少ないことも現金が好まれる理由の一つかもしれません。
キャッシュレス決済が普及している国
日本のお隣の韓国や中国はキャッシュレス決済がとても進んでいると言われています。キャッシュレス決済が進んでいる国では、国の方針としてキャッシュレス決済を普及させるためのさまざまな取り組みが行われています。スマートフォンが1台あれば、社会の全ての場所で支払いができる便利な時代がもうすぐそこまで来ています。
お金を見ればその国がわかる?お金には国の特徴が現れている
お金の名前やデザインには、その国や地域が大切にしている歴史や価値観が現れています。日本のお金に描かれている人や建造物の歴史を調べて、なぜその人達が選ばれたのか想像してみるのも面白いかもしれません。
また、お金が国境を超えて日々取引されている現状では、それぞれの国に対する期待や信頼がお金に反映されることもあります。お金には世界の過去、現在、未来の情報が詰まっているので、お金の勉強は皆さんの将来にとって、いろいろな意味で役立つと言えるでしょう。