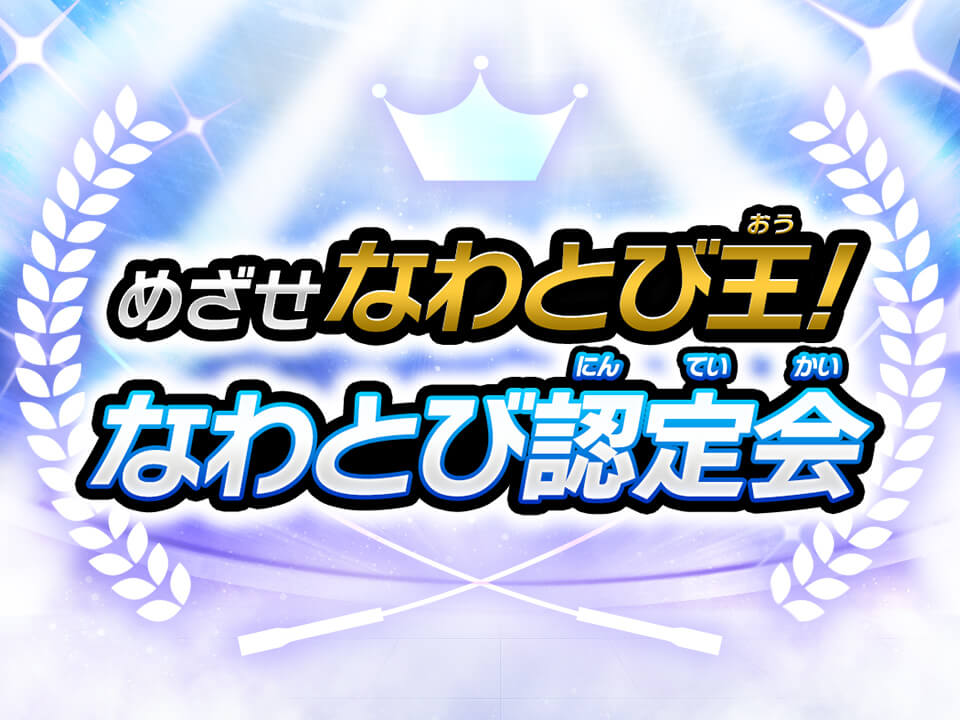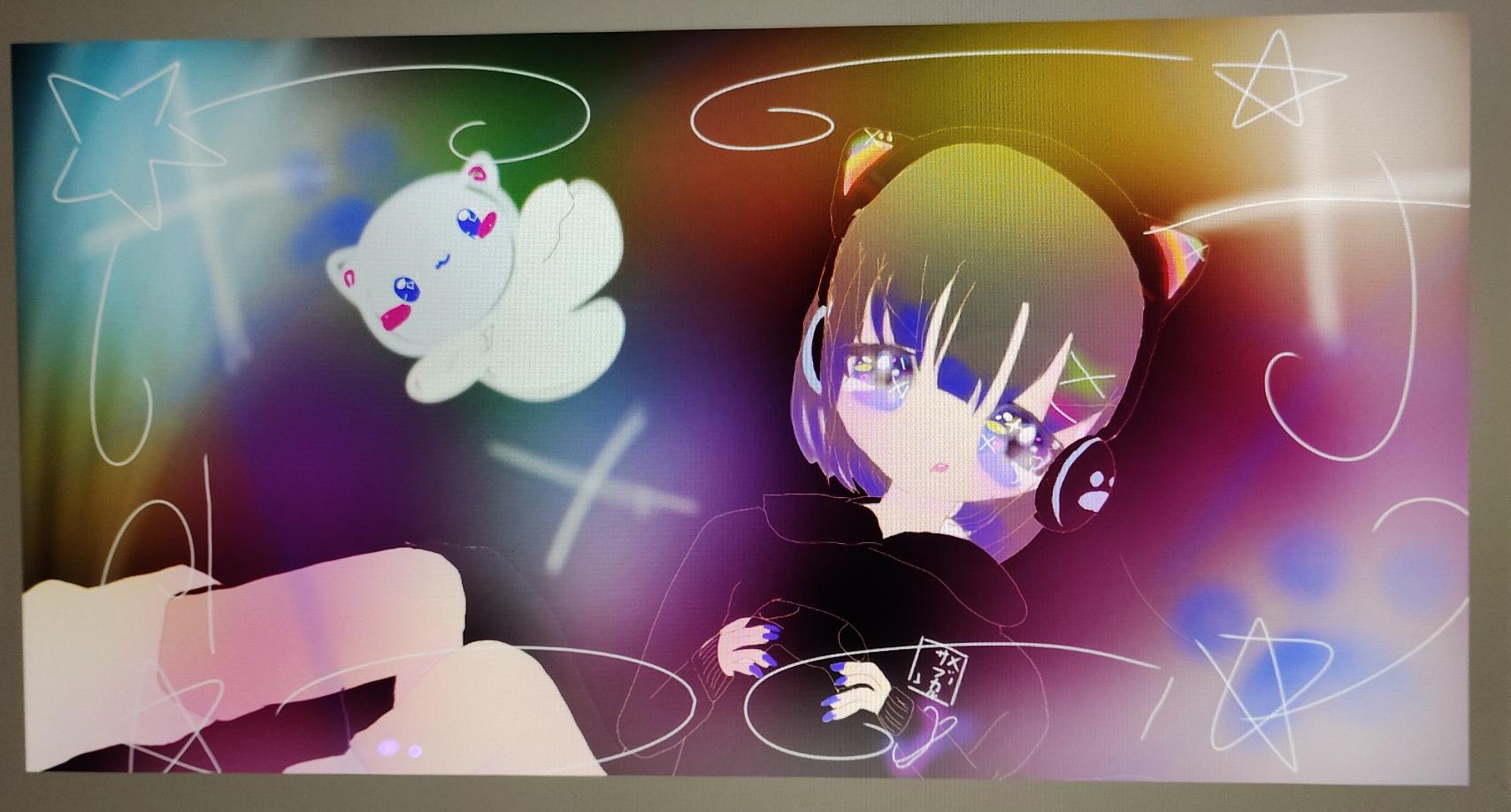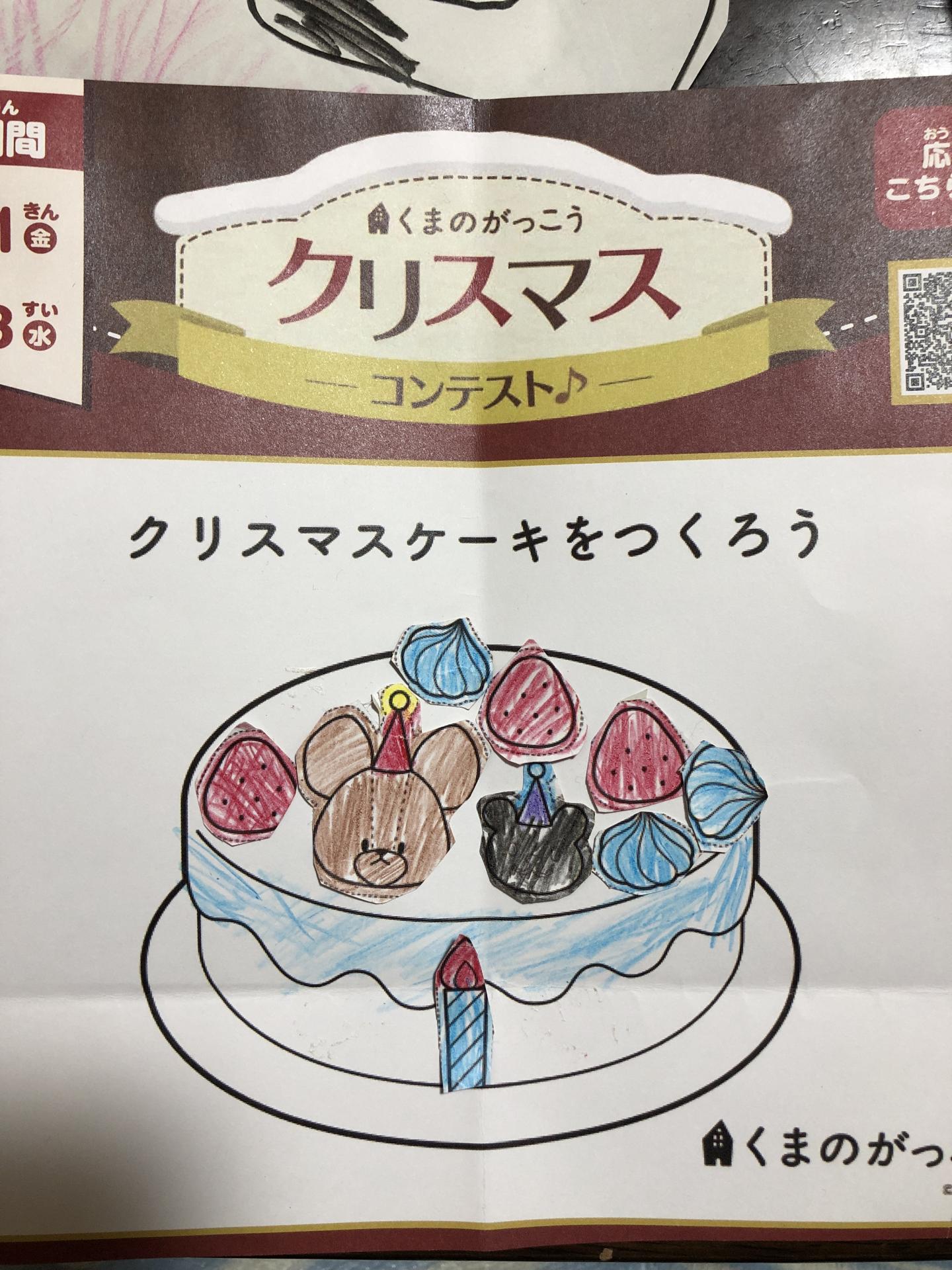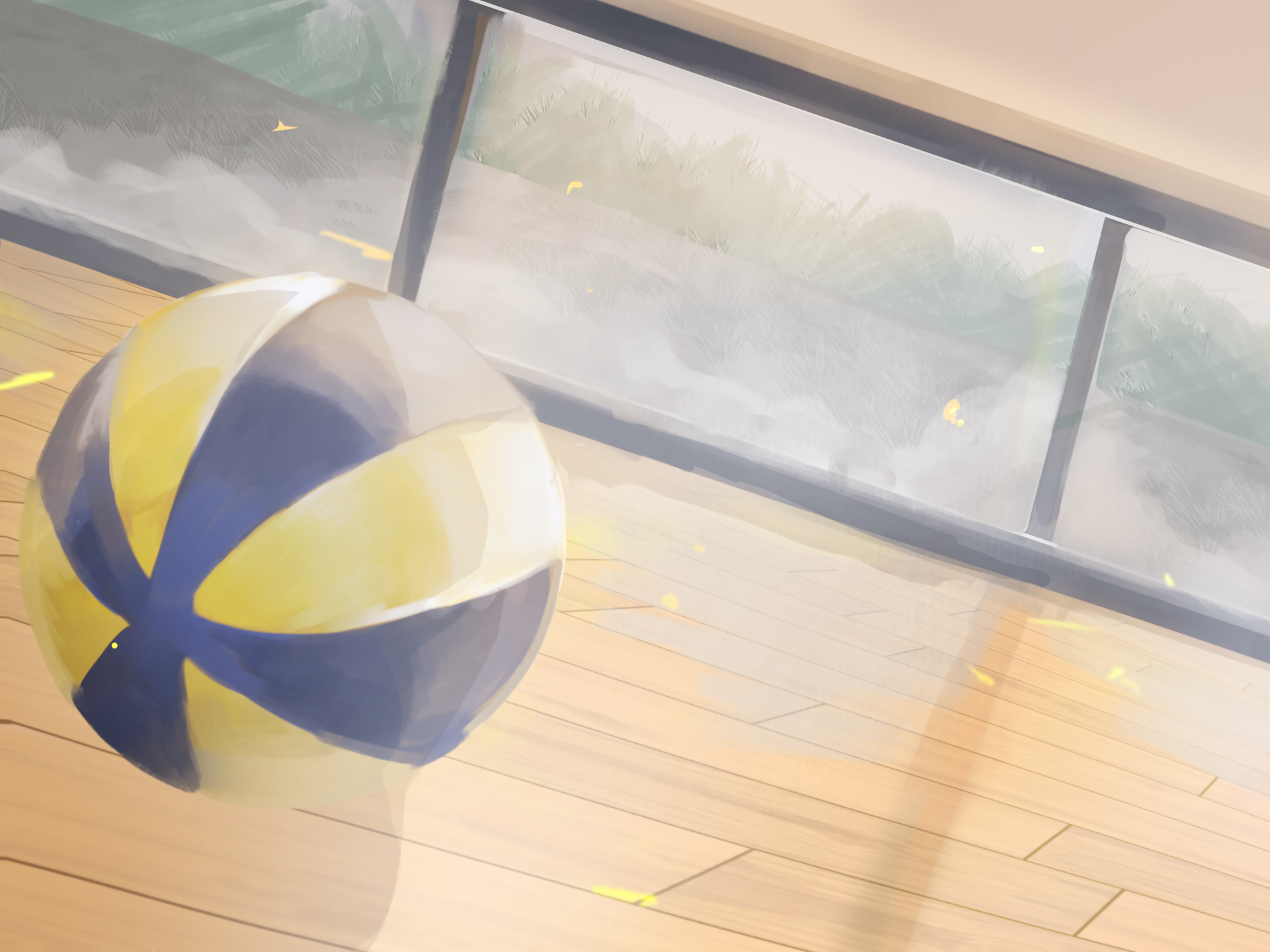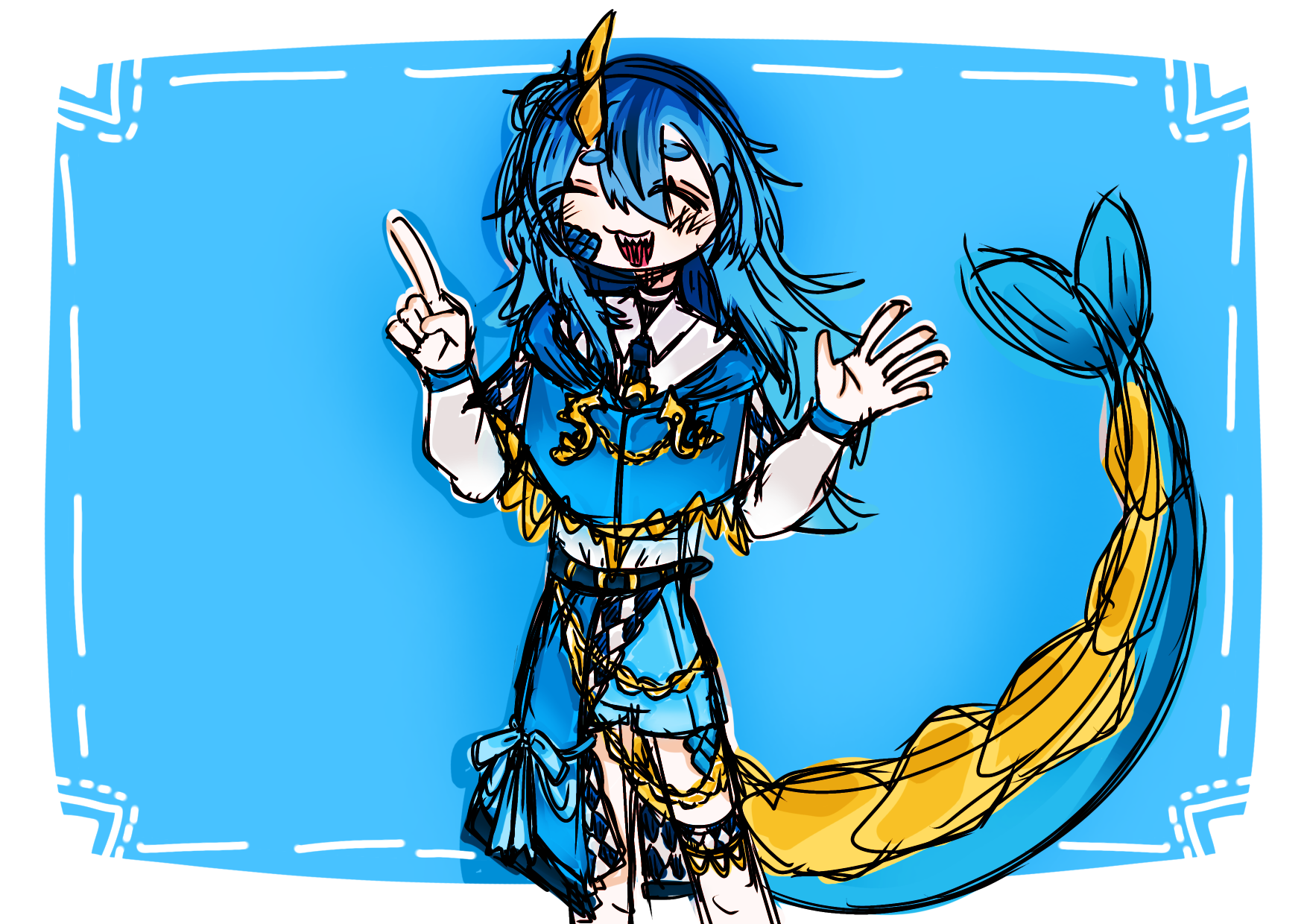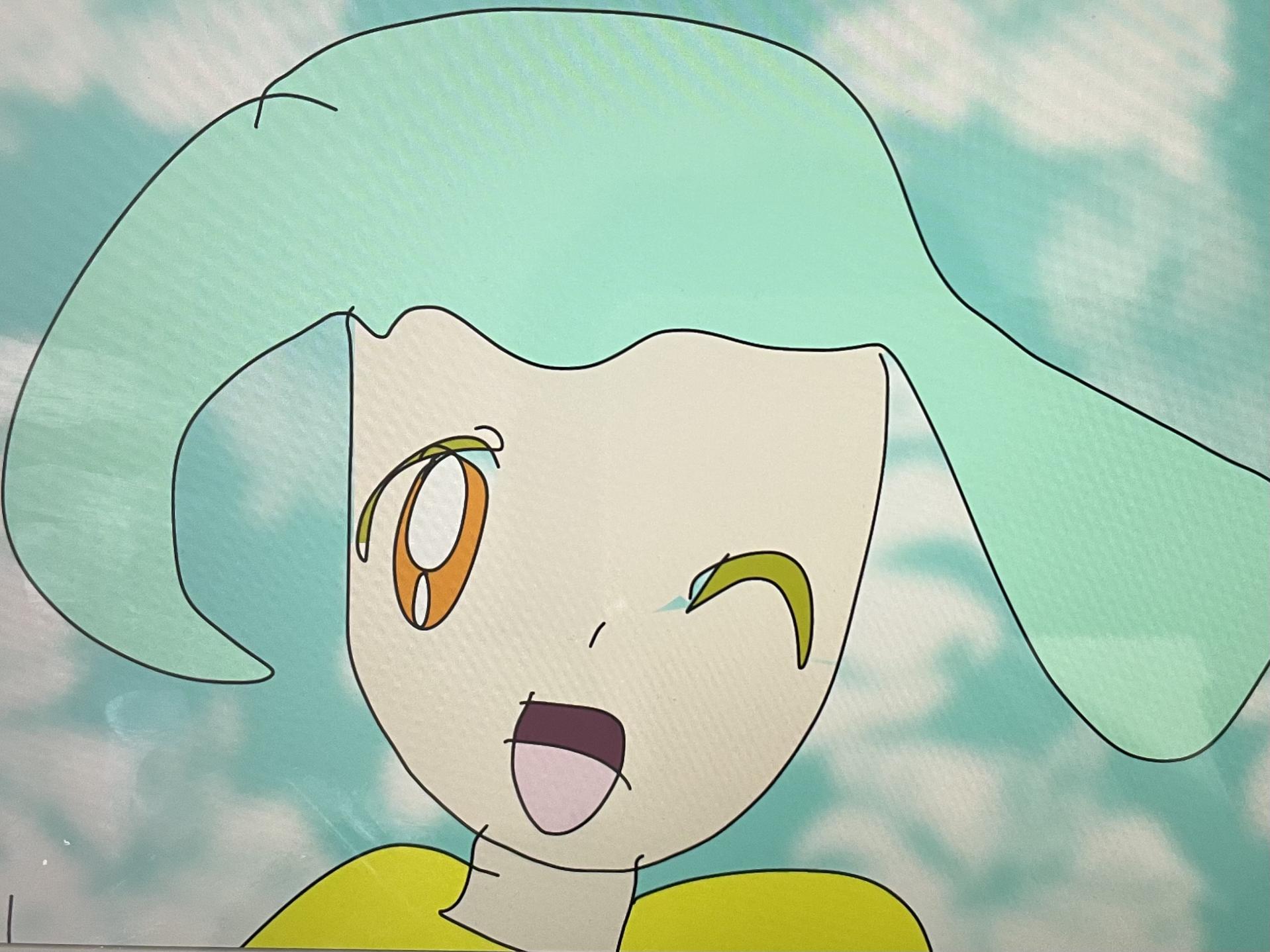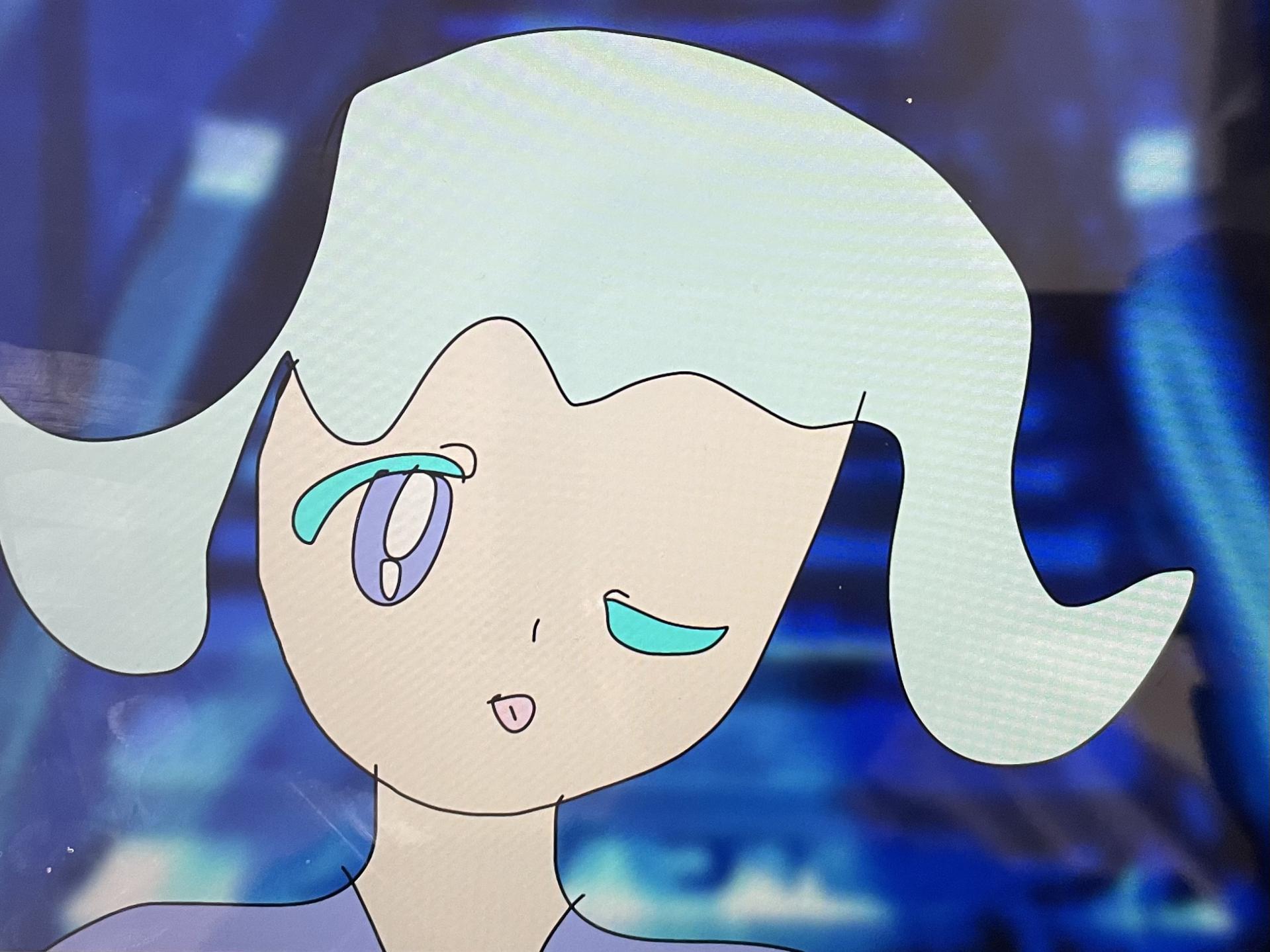モーターは電気の力で物体を回転させる道具で、身の回りにあるさまざまな製品に利用されています。モーターの回転を上手に利用すると、タイヤを動かして車を走らせたり、扇風機の羽を回して風を作り出したりといった生活に役立つ働きが生まれます。 電気のエネルギーを回転する動きに変えるために、モーターの中にはどのような仕掛けが組み込まれているのでしょうか?
この記事をいいねと思ったらクリック!
モーターの仕組み

モーターは電気のエネルギーを使って、回転する力を生み出す装置です。このモーターの働きには、電気の力と磁石の力、そして物を動かす力の3種類の力の不思議な関係が利用されています。モーターの種類によって構造が異なる場合がありますが、ここでは、ブラシ付きDCモーターという種類のモーターを例に解説します。
電気と磁力の関係
まずは、電気と磁石の力(磁力)の関係を見てみましょう。電気の流れ(電流)が生じると、電流の周りを回るような磁力が発生します。右手を握って親指だけを立てた「イイね」のポーズはこの2つの力の関係を説明するのによく使われます。親指の向き(上向き)の電流が流れると、残りの4本の指の向きに磁石の力が働きます。親指を下に向けると、残りの指の回転方向が逆向きに変わるように、電気を流す方向を逆転させると磁石の力も逆向きになります(親指を下に向けるポーズはとても失礼な意味があるので、人に向けてやってはいけません)。
モーターの構造
モーターの基本的な構造は、2つの永久磁石で挟まれた空間に、電気が流れる導線をコイル状に巻いた部品を配置したものです。この部品は電気が流れた時だけ磁石になる「電磁石」として働きます。電磁石に流れる電流の方向を変えると、磁石の力の向きが逆転する性質があります。
永久磁石は、学校の授業などで使われる普通の磁石と基本的に同じものです。モーターの場合は、永久磁石のN極とS極が電磁石を挟むように配置されます。
この構造のポイントは、2つの永久磁石の間に働く磁石の力と、電磁石による磁石の力の両方が働くことです。次に、この構造が回転する力を生み出す仕組みを考えてみましょう。
電気と磁石が作る第三の力
ここまで電気と磁石の力の関係を見てきましたが、モーターの回転を理解するためには、もう一つの力である「物体を動かす力」が重要です。実は、磁石の力が働いている空間(磁界)で電気を流すと、物体を動かす力(電磁力)が発生します。
この3つの力の関係性は、「フレミング左手の法則」と呼ばれ、左手の親指、人差し指、中指の3本の方向で表現されます。手のひらを大きく開いた状態で、中指を根元から90度曲げると、3本の指がそれぞれ直角に交わっているような形ができます。この時、中指の方向が電気の流れ、人指し指が磁石、親指が物体を動かす力の方向を表しています。人差し指(磁石)の向きを変えずに、手をひねって中指(電気)の向きを反対にすると、親指(物体を動かす力)の向きが逆転することが分かります 。
モーターが回転する仕組み
電気を同じ方向に流し続けている間は電磁力の向きも変わらないので、そのままでは物体を回転させることができません。そこで、モーターは電気を流す方向とタイミングをうまくコントロールして、回転力を生み出しています。
ここでも手を使ってモーターの働きをイメージしてみましょう。人差し指と親指をU字型にして、電気が流れる経路とします。例えば、電気が人差し指の先から入って、指の付け根を通って親指に流れ、親指の先から出ていくような構造です。この時、人差し指と親指では電気の流れる向きが反対なので、逆向きの電磁力が働きます。人差し指は上向き、親指は下向きに動くとすると、手首を左に回転させるような力が働きます(右手の場合)。
このままでは、人差し指が真上に来たところで止まってしまいますが、実際のモーターでは、真上に来る直前で電気を止めて、電磁力が発生しないようにします。すると、残った勢いで回転が続き、人指し指が真上を越えていきます。さらに、ここで電流の方向を反対にすると、人差し指に下向きの電磁力を発生さするので、さらに回転が続きます。
回転に合わせて電流をストップする仕掛けと、電流を反転させる仕掛けとして、モーターには、ブラシと整流器(コミテーター)と呼ばれる部品が組み込まれています。これらの部品が電流の向きと流れるタイミングの調節で、モーターの速い回転運動が実現できます。
モーターの種類

これまでに、特徴が異なるいくつかのタイプのモーターが開発されています。それぞれ優れている点や価格などが違うので、使用したい場面に適したモーターを選べます。モーターの特徴に特に関係するのは、モーターに流す電流の種類の違いです。
DC(直流)モーター
DCモーターは、直流(Direct Current)の電流を使って回転するモーターです。直流とは、電気の流れる向きや大きさ、電圧が変化しない電気の流れ方のことです。直流の代表的なものは乾電池から流れる電流です。
DCモーターは回転速度制御がしやすい特徴があります。低い電圧でも使用できるうえ、価格も安価なものも多く、家庭用の小型電気製品から精密なコントロールが必要なものまで、幅広い用途に活用されています。
AC(交流)モーター
ACモーターは、交流(Alternating Current)の電流を使うモーターです。交流は、電気の流れる向きや大きさ、電圧が周期的に変化する電気の流れ方です。皆さんの家にあるコンセントから流れる電流は交流です。
交流では電気の流れの流れる向きが周期的に変化する、という説明でピンときた人もいるかもしれませんが、ACモーターではこの交流の特性を使って回転を生み出しています。そのため、電流が変化する周期(周波数)がモーターの回転に影響を与え、速度の制御がやや複雑になってしまうデメリットがあります。
ACモーターは大きなパワーが必要な場面に適しているので、工場などで産業用に使われるほか、電気自動車(EV)やハイブリッドカーで使われることもあります。
モーターが使われている場面

モーターの機能は物体を回転させるシンプルなものですが、使い方の工夫で社会のあらゆる場面で役立っています。
モーターを使っている家庭にある機械
換気扇や扇風機のように回転が目に見えるものはもちろんですが、目に見えない場所でモーターが働いているものもあります。例えば、電気髭剃り機では、刃をモーターで高速回転させています。また、スマートフォンやゲーム機のコントローラーについている振動機能は、モーターの回転軸に偏った重りを付けたもので実現されています。
社会で使われているモーター
EVやハイブリッドカーでは、タイヤを回転させるためにモーターが使われています。ガソリンなどを燃焼させるエンジンと違って、音が静かな車をたくさん見かけるようになりました。また、電車を動かすためにもモーターが使われています。
近年では、モーターの回転を状況に合わせて精密に制御できる技術が発達したこともあり、ロボットの動作に活用されることが増えています。
モーターの作り方

モーターの原理や構造は複雑で難しいと思われるかもしれませんが、実は簡単に手に入る道具を使って、すぐにモーターの原理を再現できます。
家庭でできる簡易モーターの詳しい作り方は下記の記事で紹介しています。自分で作ってみると、よりモーターの原理を理解しやすくなるので、自由研究のテーマとして取り組んでみるのもおすすめです。
モーターは電気の力の素晴らしい活用法
モーターの仕組みを見ると、電気や磁石の性質を上手に活用して回転する力を生み出していることが分かりました。また、その回転に一工夫加えることで、私たちの生活を豊かにする便利な道具を作ることもできます。
モーターのように、中学校や高校の授業で学ぶような基本的な科学法則が便利な発明につながることを知っていると、勉強がさらに楽しくなるかもしれませんね。