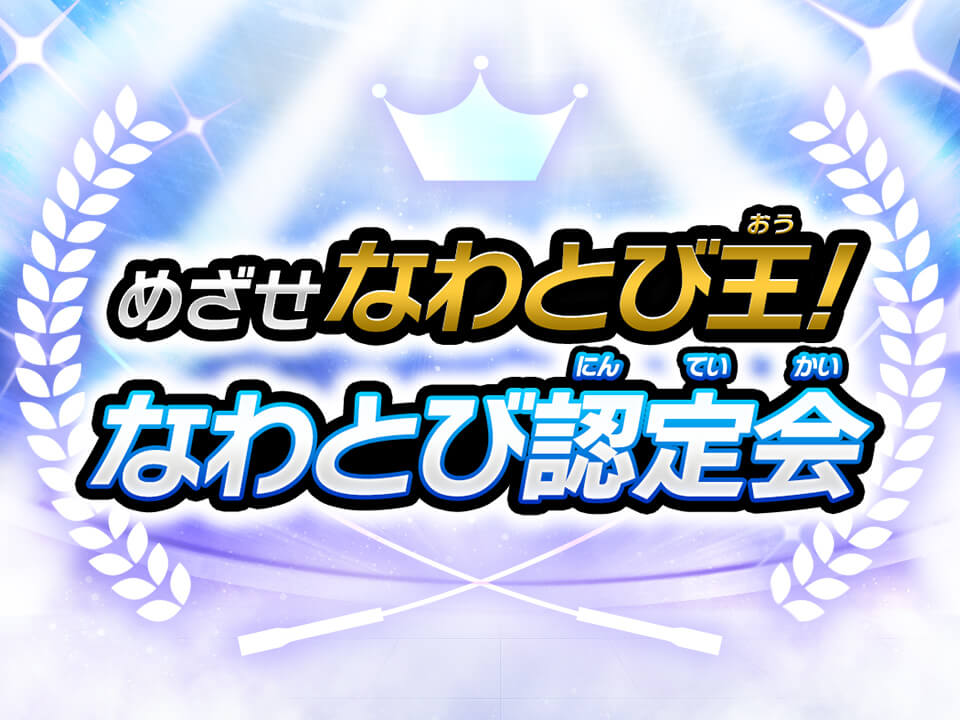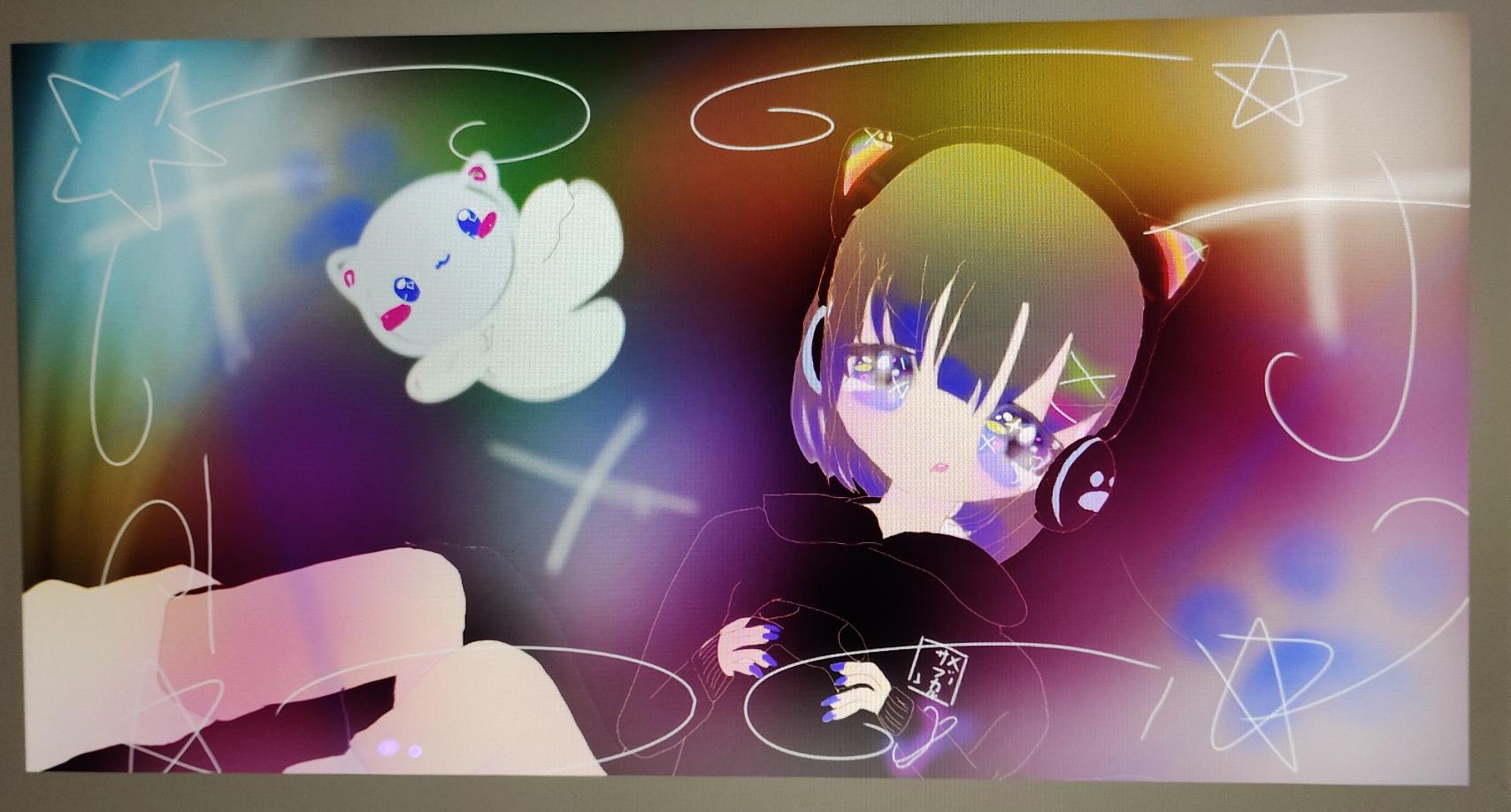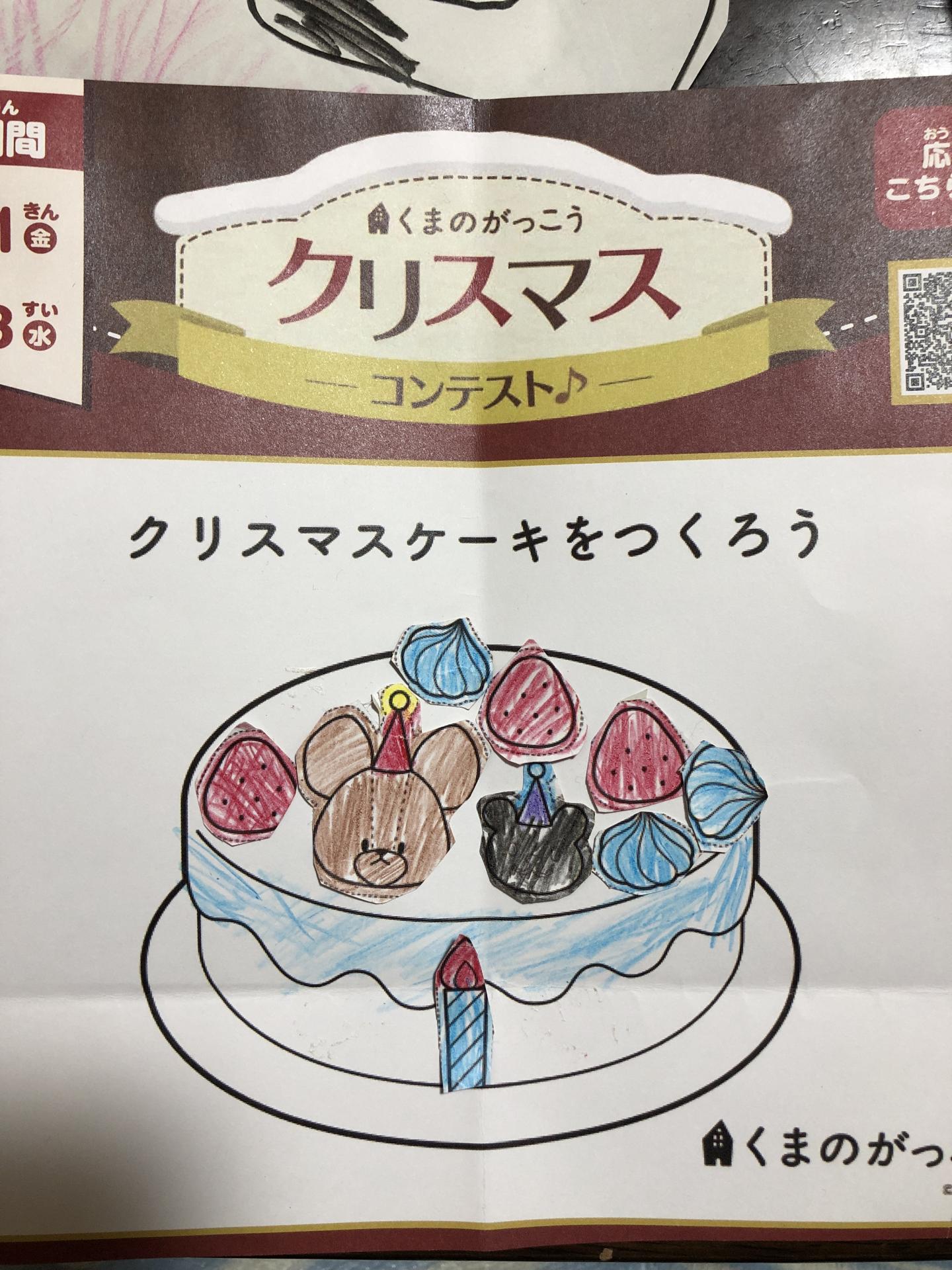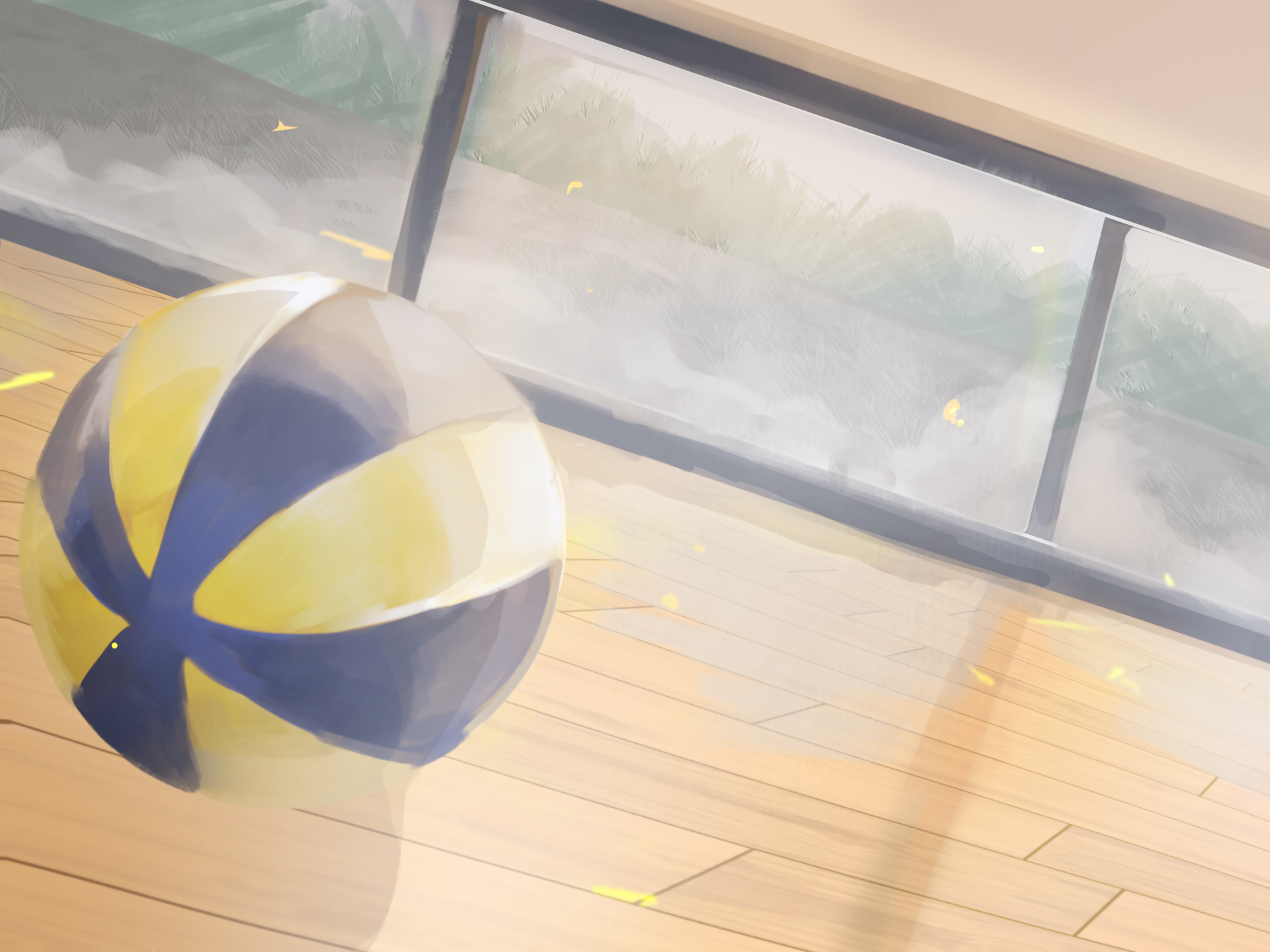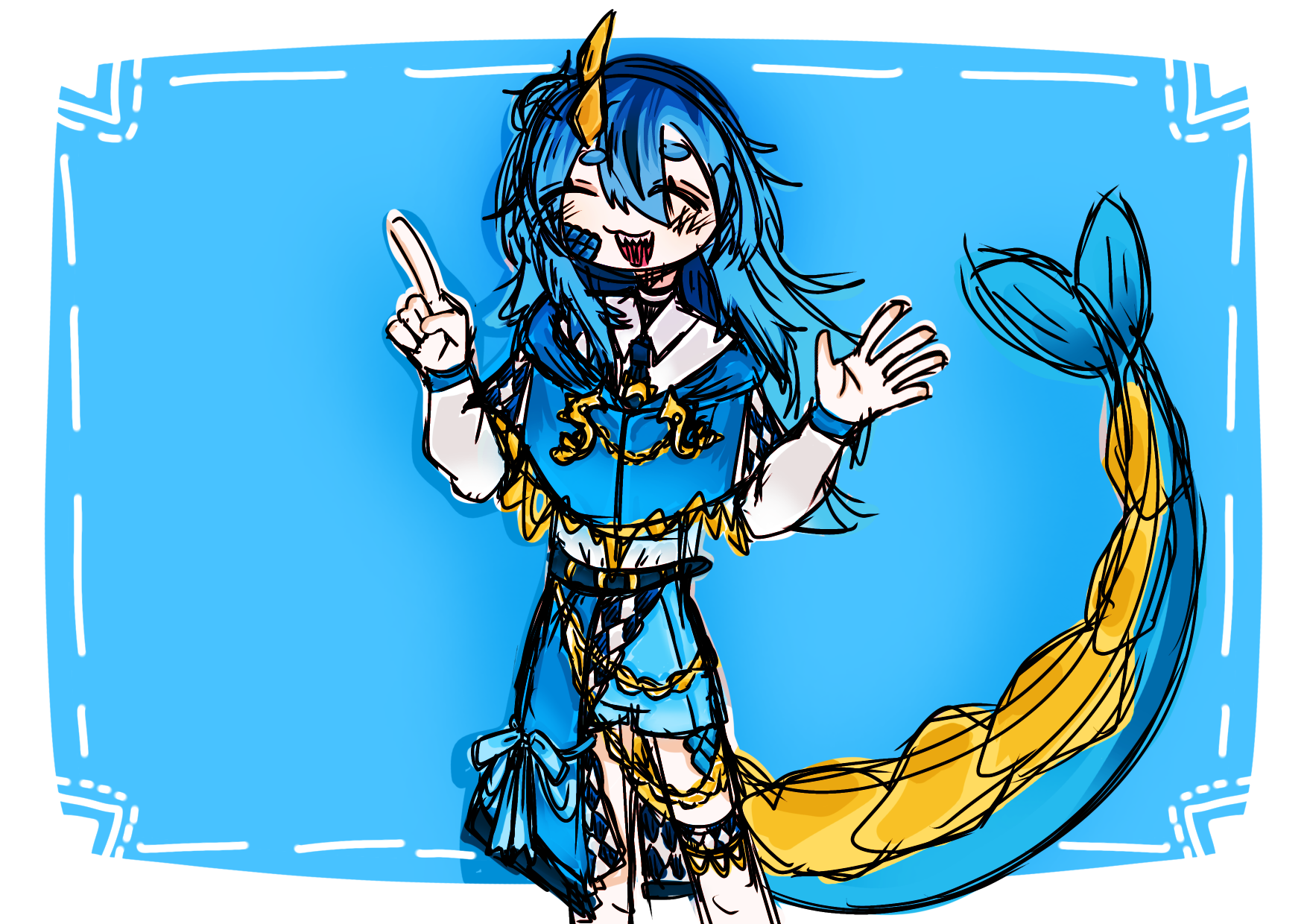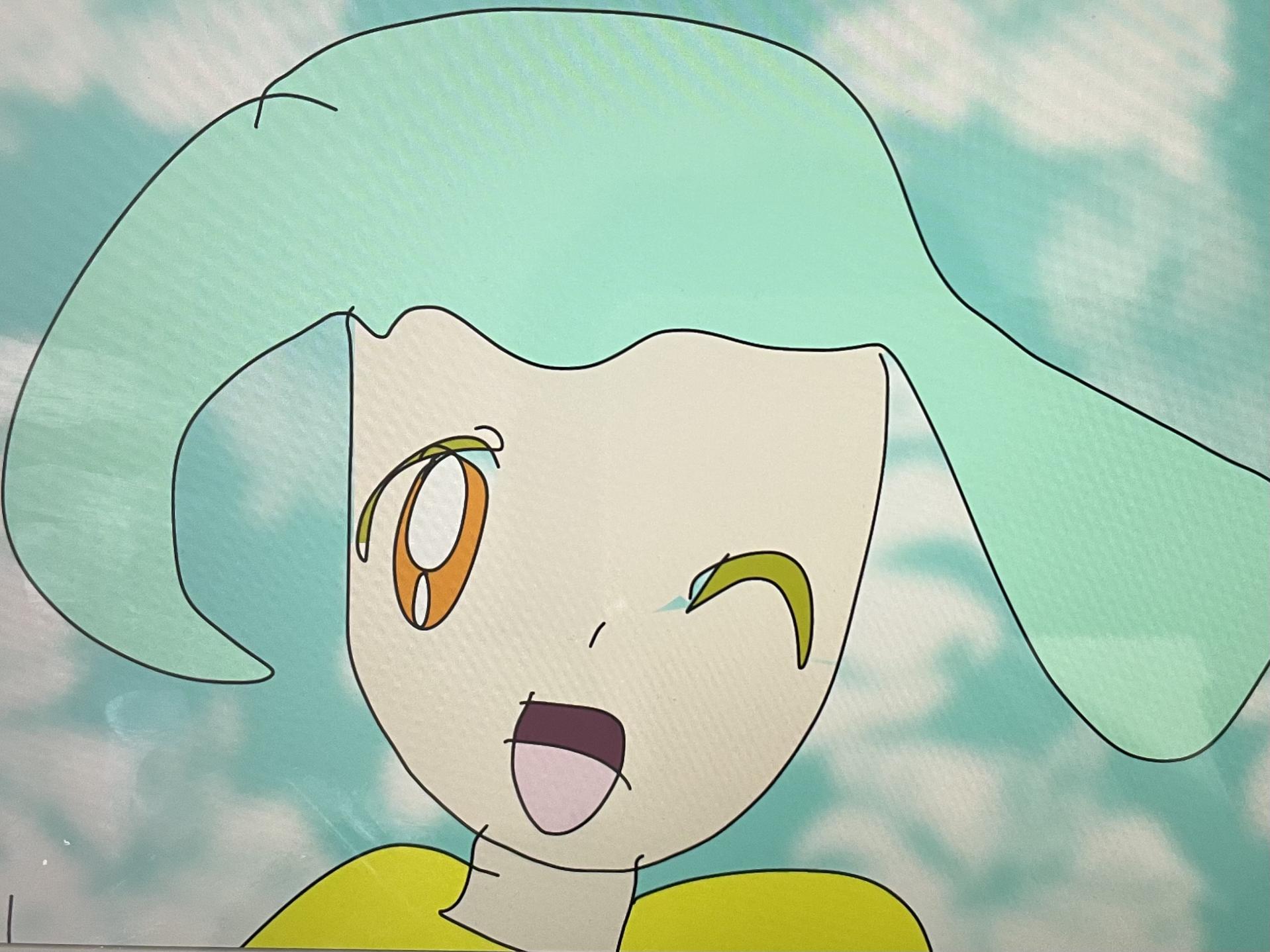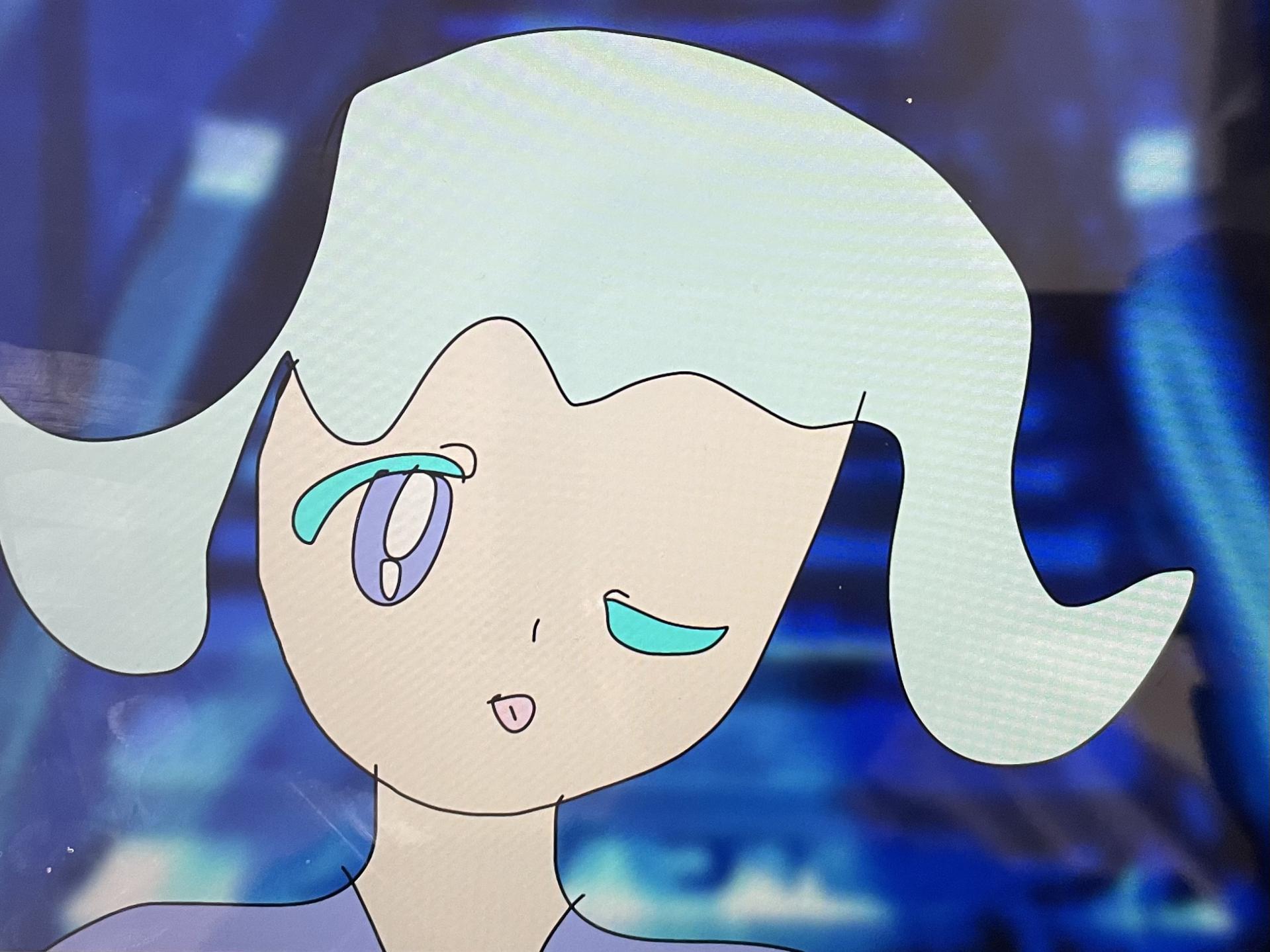ゴールデンウイーク(GW)は日本の大型連休で、旅行や家族との時間を楽しむ人が多い特別な期間です。しかし、ゴールデンウイークという名前の由来や、どんな経緯で祝日になったのかについては、知られていないことも多いです。この記事を読んで、知らなかったゴールデンウイークのヒミツを、いっしょに探ってみましょう!
この記事をいいねと思ったらクリック!
この記事のもくじ
ゴールデンウイーク(GW)の由来は?

ゴールデンウイークは、毎年4月の終わりから5月のはじめにかけて続く長いお休みです。学校がお休みになり、旅行に行ったり、家族と出かけたりする人も多いですね。しかし、「ゴールデンウイーク」という名前の由来を知っていますか?
・【その1】ゴールデンウイークは映画業界から生まれた言葉!
ゴールデンウイークという言葉は、もともと映画業界で生まれました。いくつか説がありますが、一番有名なのは、映画会社が考えたというものです。
昔の日本では、春の終わりごろになると映画館がにぎわいました。暖かくなって外出しやすくなることに加えて、祝日が多く、お休みが続く時期だったからです。特に4月の終わりから5月の初めにかけては、多くの人が映画を楽しんでいました。そのため、映画会社にとっても、お客さんが増える大切な時期だったのです。そこで、「もっと多くの人に映画を見てもらうために、このお休みに特別な名前をつけよう」と考えました。そのときにヒントになったのが「ゴールデンタイム」という言葉です。
・【その2】名前の由来は「ゴールデンタイム」に習ったもの
「ゴールデンタイム」とは、視聴率が高く、最も多くの人がテレビを見る時間帯のことです。たとえば、夜7時から9時ごろは、家族みんなでテレビを見ることが多い時間帯ですよね。この時間は特に注目される時間とされていて「ゴールデン(黄金の)」という言葉が使われています。
映画会社はこの考え方を参考にして、「多くの人が映画を楽しめる特別なお休みの時期だから、ゴールデンウイークと呼ぼう」と決めました。
・【その3】「黄金週間」から「ゴールデンウイーク」へ
実は、最初は「黄金週間(おうごんしゅうかん)」という名前も使われていました。「黄金」とは、金色のことです。昔から金はとても価値のあるものとされているので、「特別な一週間」という意味をこめて、「黄金週間」と呼ばれていたのです。
しかし、「黄金週間」よりも「ゴールデンウイーク」のほうの響きがよく、インパクトがありました。そのため、次第に「ゴールデンウイーク」という言葉が広まり、今では多くの人がこの呼び方を使うようになったのです。
ゴールデンウイークにはどんな祝日があるの?

ゴールデンウイークにあるいくつもの祝日には、それぞれ大切な意味や由来があります。
・4月29日「昭和の日」
「昭和の日」は、昭和という時代をふり返り、日本がどのように発展してきたのかを考える日です。昭和の時代には、戦争や経済の発展など、いろいろな出来事がありました。この日を通して、昔の日本のことを知るきっかけになるかもしれません。
・5月3日「憲法記念日」
5月3日は「憲法(けんぽう)記念日」です。日本国憲法が1947年(昭和22年)のこの日に施行されたことを記念して作られた祝日です。
日本国憲法は、国の大切な決まりごとをまとめたものです。とくに「平和を大切にすること」「国民の自由や権利を守ること」などが書かれています。この日は、日本の法律や平和について考える機会になっています。
・5月4日「みどりの日」
5月4日は「みどりの日」です。この日は、自然を大切にし、緑に親しむことを目的とした祝日です。公園や森へ出かけたり、植物を育てたりするのも、みどりの日の過ごし方の一つですね。
・5月5日「こどもの日」
5月5日は「こどもの日」です。この日は、子どもたちが元気に育つことを願う祝日です。また、親に感謝する日でもあります。
昔から5月5日は「端午の節句(たんごのせっく)」と呼ばれ、男の子の成長を祝う日でした。その名残で、今でもこいのぼりを飾ったり、かしわもちを食べたりする風習があります。
こどもの日は、男の子だけでなく、すべての子どもたちの健やかな成長を願う日として祝われています。
ゴールデンウイークはいつからあるの?

ゴールデンウイークのもとになる祝日ができたのは、1948年(昭和23年)です。この年に「国民の祝日に関する法律」が作られて、5月3日が「憲法記念日」、5月5日が「こどもの日」として祝日になりました。
それ以前、4月29日は「天皇誕生日」として祝日でしたが、昭和天皇の崩御(ほうぎょ:亡くなること)により、1989年(平成元年)にこの日は「みどりの日」に変わりました。
また、1985年に祝日法が改正されて、「祝日の間にはさまれた平日も休みにしよう」という新しいルールができました。これによって、5月3日と5月5日の間にあった5月4日も「国民の休日」となり、5月3日から5日までが毎年連休になりました。
さらに、2007年には5月4日が「みどりの日」と正式に決まり、4月29日は「昭和の日」となりました。
こうして、祝日が増えていき、4月29日から5月5日まで多くの人が休めるようになり、ゴールデンウイークは日本の大きな連休として定着していったのです。
ゴールデンウイークは海外にもあるの?

ゴールデンウイークは、日本の長期休暇で、多くの人が旅行やリラックスした時間を楽しみます。それでは、海外にも日本と同じようにゴールデンウイークのような長期休暇があるのでしょうか?海外の長期休暇について見ていきましょう。
・ゴールデンウイークは日本にのみ存在する休日!
ゴールデンウイークは、日本だけにある特別な連休です。毎年4月29日から5月5日までの間は学校や会社が休みになり、旅行に行ったり、家でゆっくり過ごしたりする人が増えます。この期間は、旅行業界などにも大きな影響を与えるため、日本の大型連休としてとても大切な時間です。しかし、ゴールデンウイークという名前の連休は、日本独自のもので、海外には同じ名前の連休はありません。
・海外にはバカンスやバケーションがある
海外にも、ゴールデンウイークのような長い休みを取る文化はありますが、名前が違います。例えば、フランスやイタリアでは「バカンス」、アメリカでは「バケーション」という言葉を使って、長期の休暇を楽しむ時期があります。バカンスやバケーションは、日本のゴールデンウイークとは少し違って、夏や冬に取ることが多いです。
ヨーロッパの国々では、特に夏の休暇が長いです。例えば、フランスでは、学校が7月初めから9月初めまで 休みになり、その間に家族で旅行に出かけることが一般的です。また、企業もこの時期に長期休暇を取ることが多く、バカンスの時期には観光地が混雑します。
また、アメリカにはゴールデンウイークのようなまとまった連休はありませんが、夏休みがとても長いのが特徴です。多くの学校では、6月から8月末、または9月初めまでの約2カ月間が夏休みになります。この間、キャンプに参加したり、海で遊んだり、遊園地に出かけたりして過ごす人が多いようです。
このように、海外にも長い休みを取る文化はありますが、ゴールデンウイークのように特定の時期に祝日が集まって連休になることは少ないです。それぞれの国で、バカンスやバケーションの時期が異なるため、休みの取り方や過ごし方は国によって違いますが、どの国でも「休むことの大切さ」は共通しています。
ゴールデンウイークは日本の大切な休暇!
ゴールデンウイークは、映画業界のアイデアから始まり、今では多くの人が楽しみにしている特別な連休となりました。旅行に出かけたり、家族と過ごしたりすることで、普段の忙しさを忘れてリフレッシュできる大切な時間です。海外の「バカンス」や「バケーション」と同じように、自分の時間を大切にすることはとても重要です。
もし次のゴールデンウイークに旅行やお出かけを計画しているなら、他の国の休暇の過ごし方にも目を向けてみると、さらに楽しくなるかもしれませんよ。自分が過ごす休みを、もっと特別なものにするために、どんなことをしてみたいか考えてみましょう。