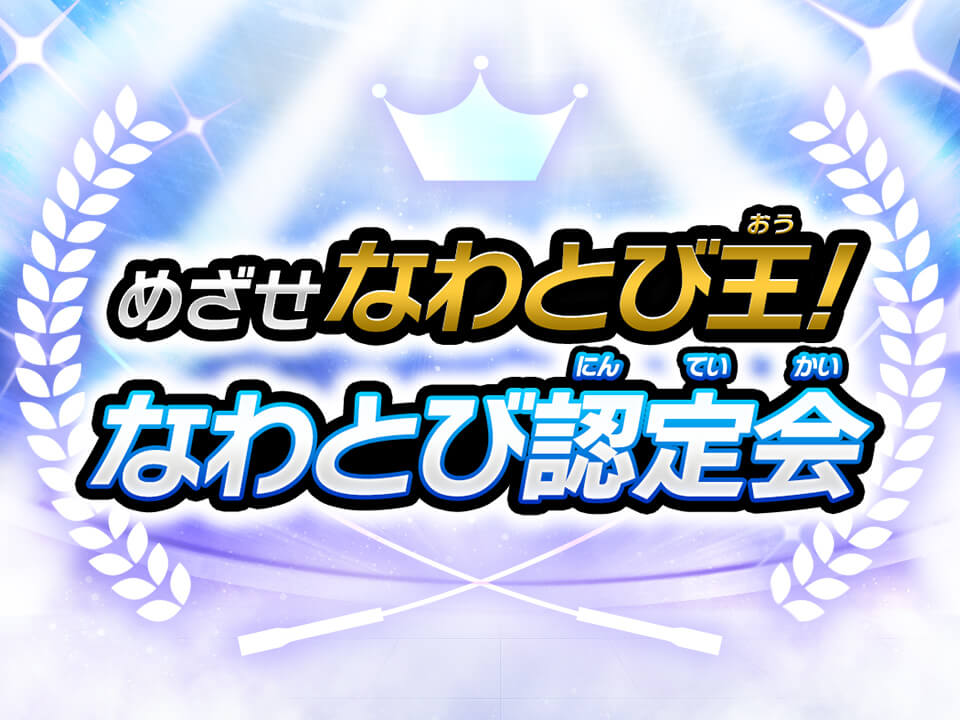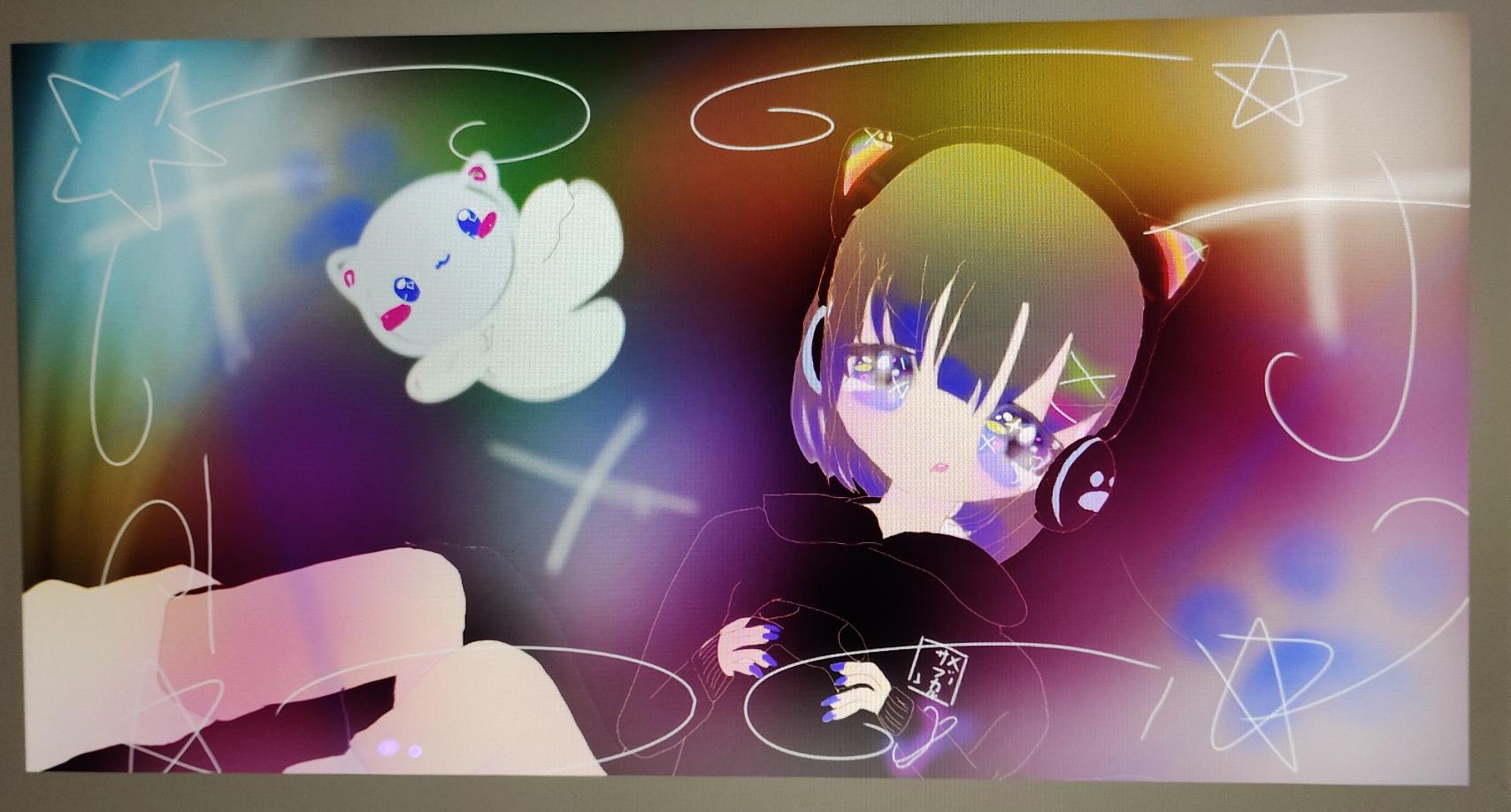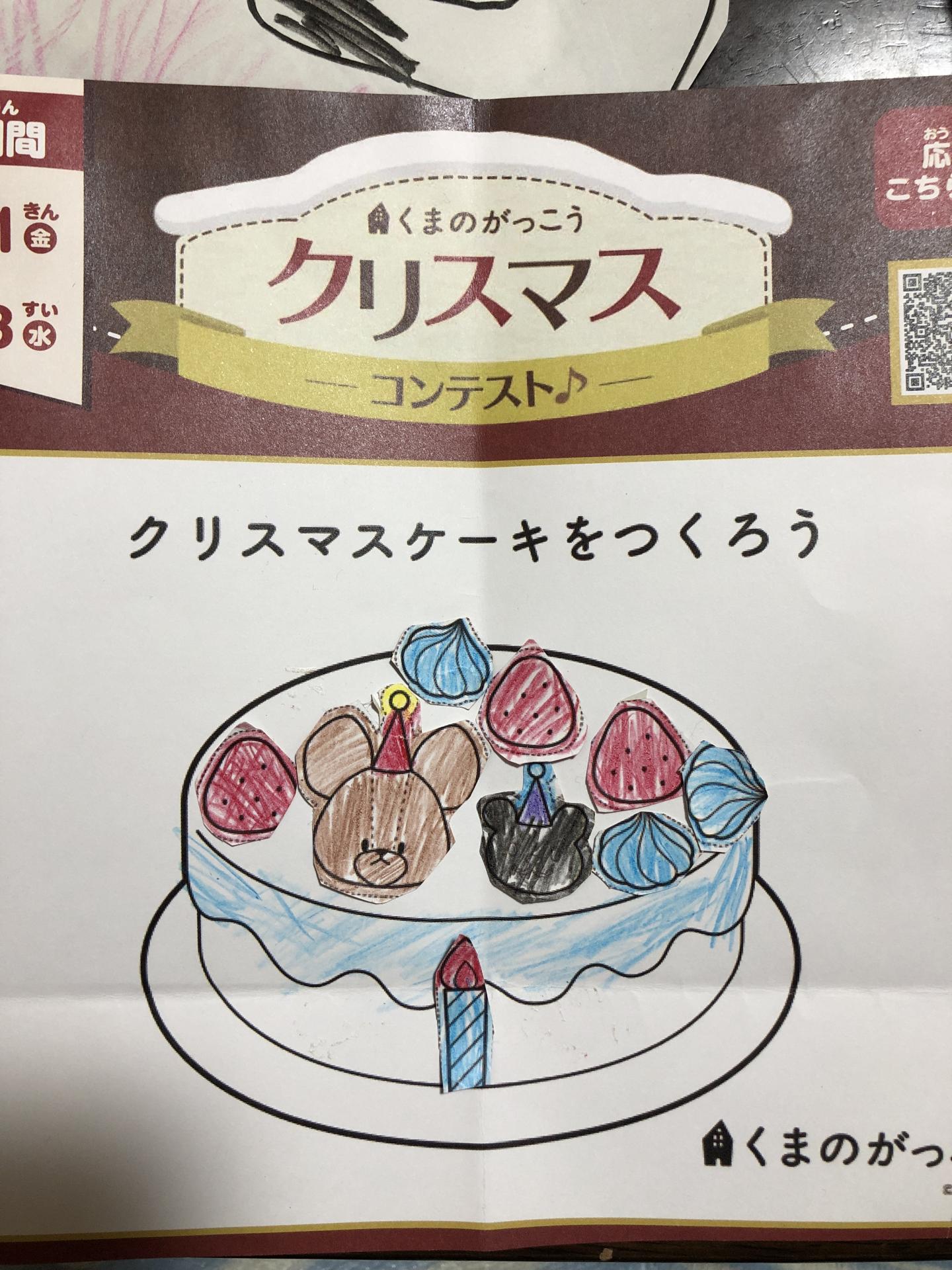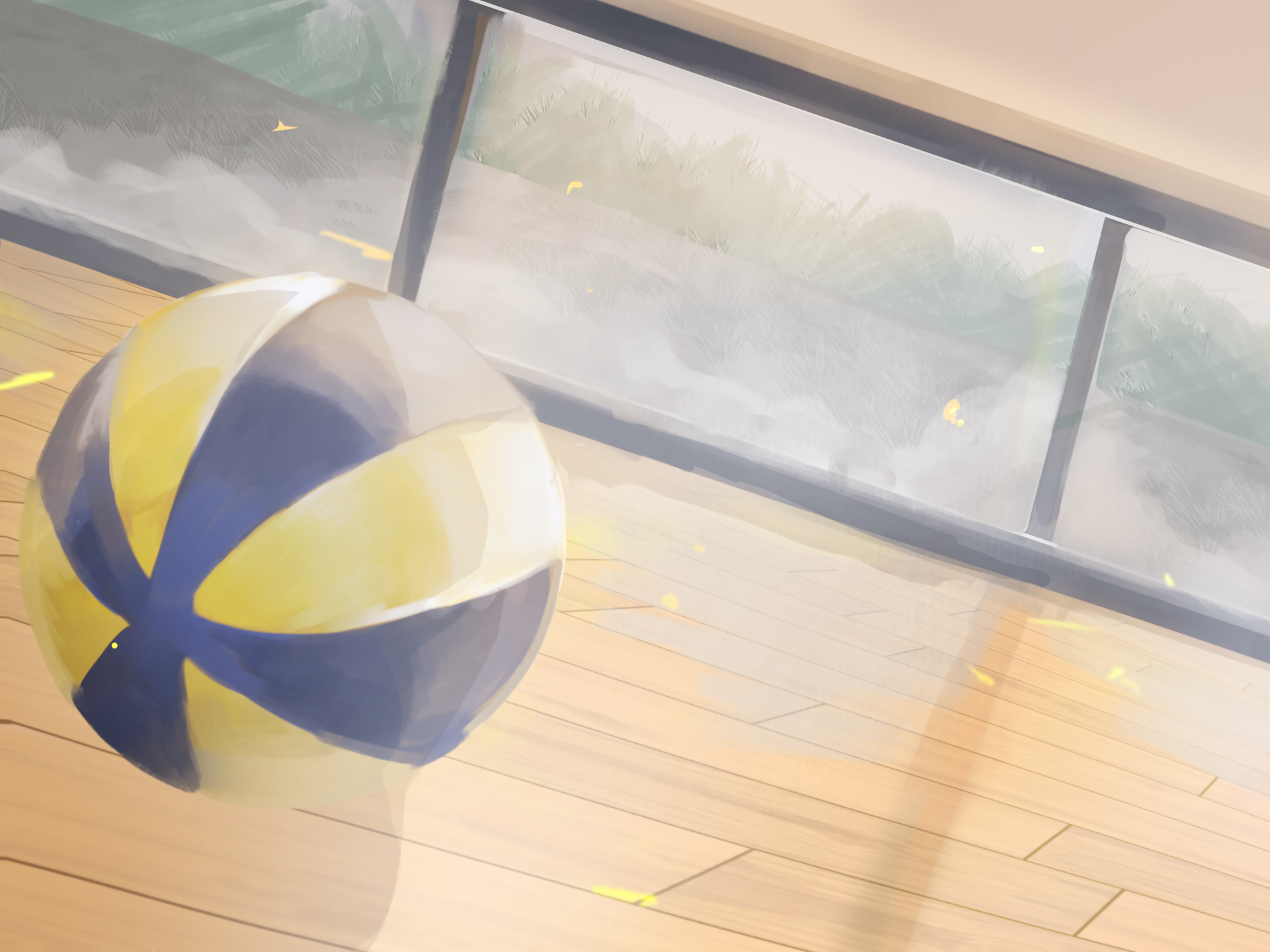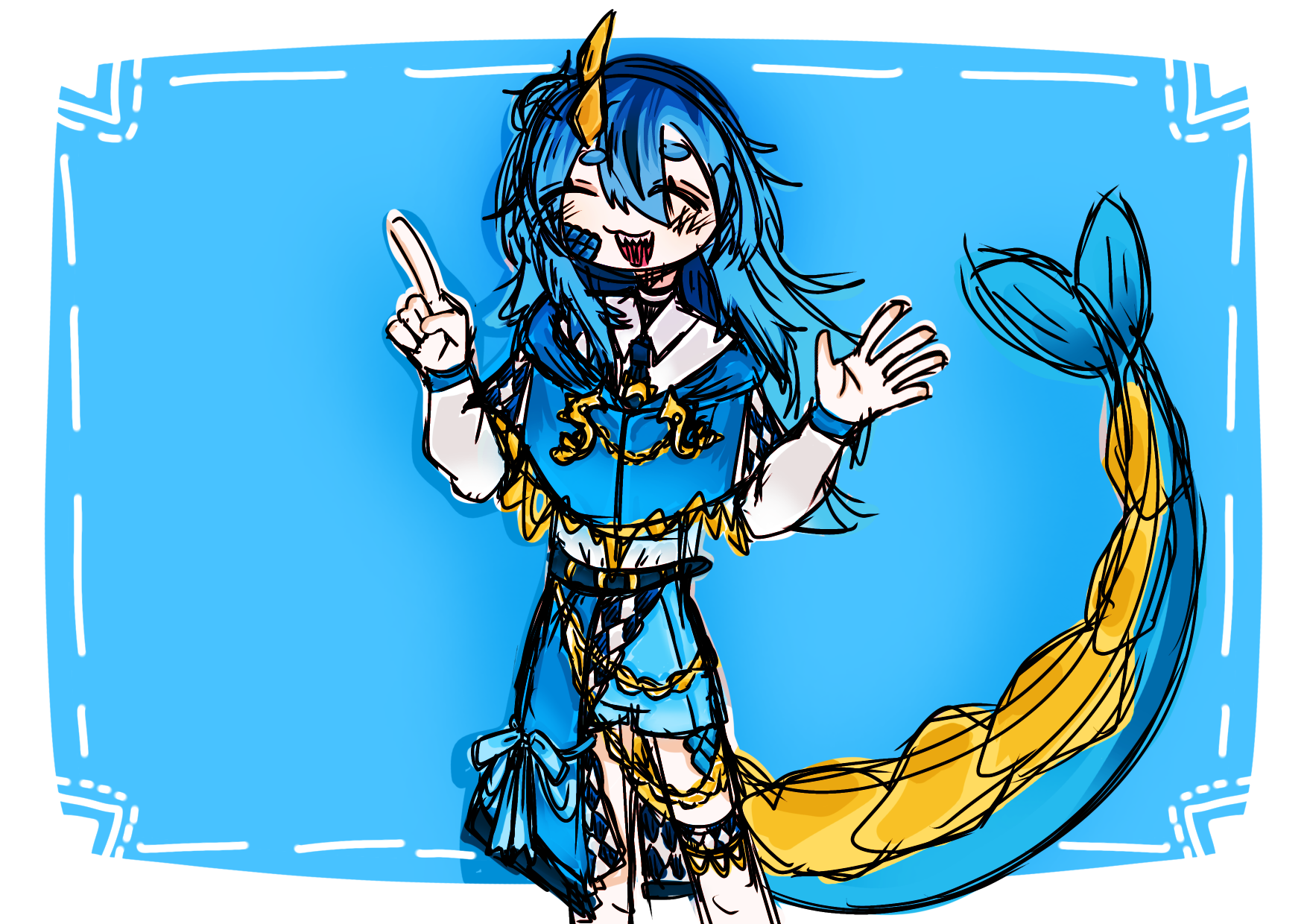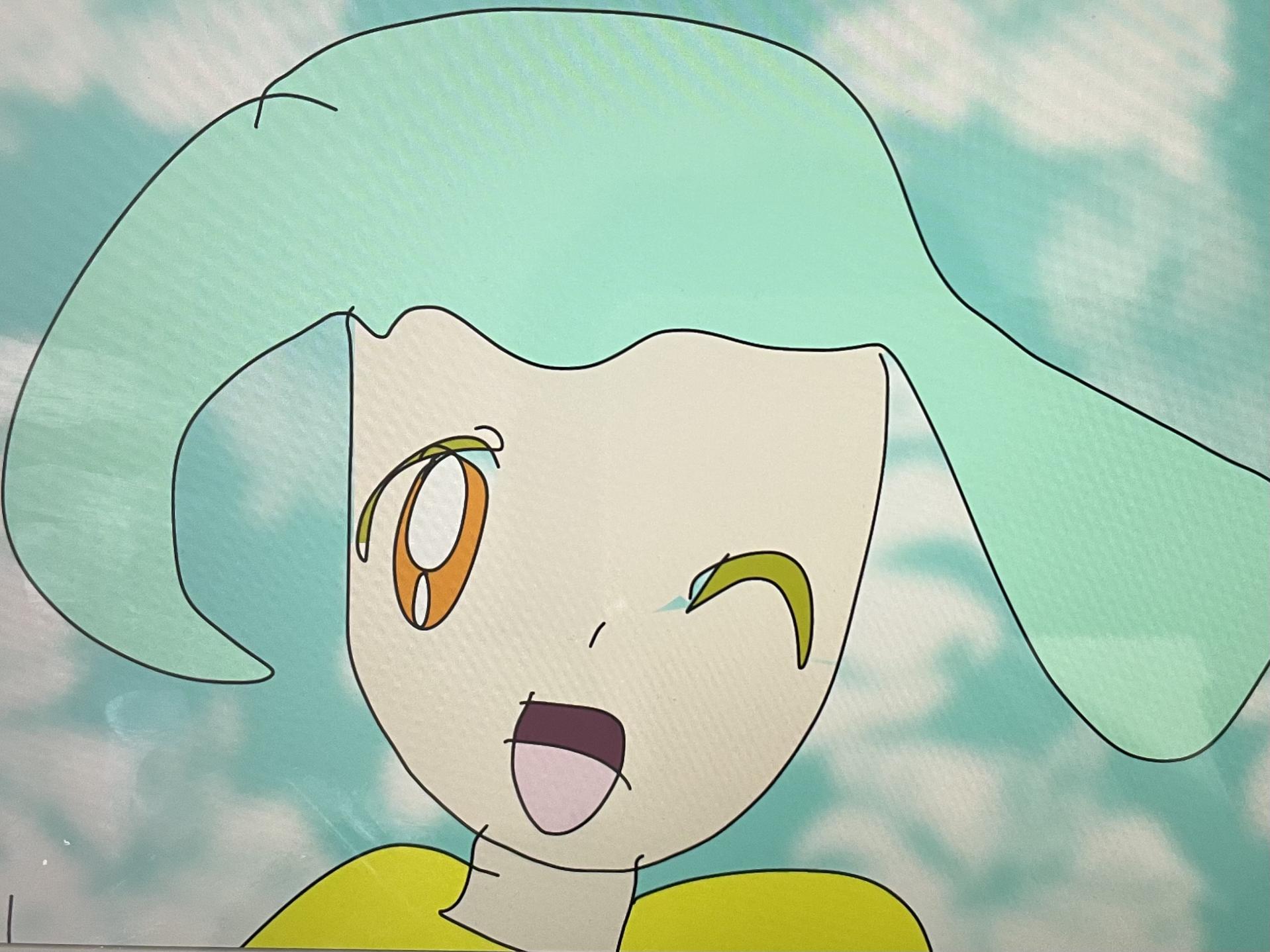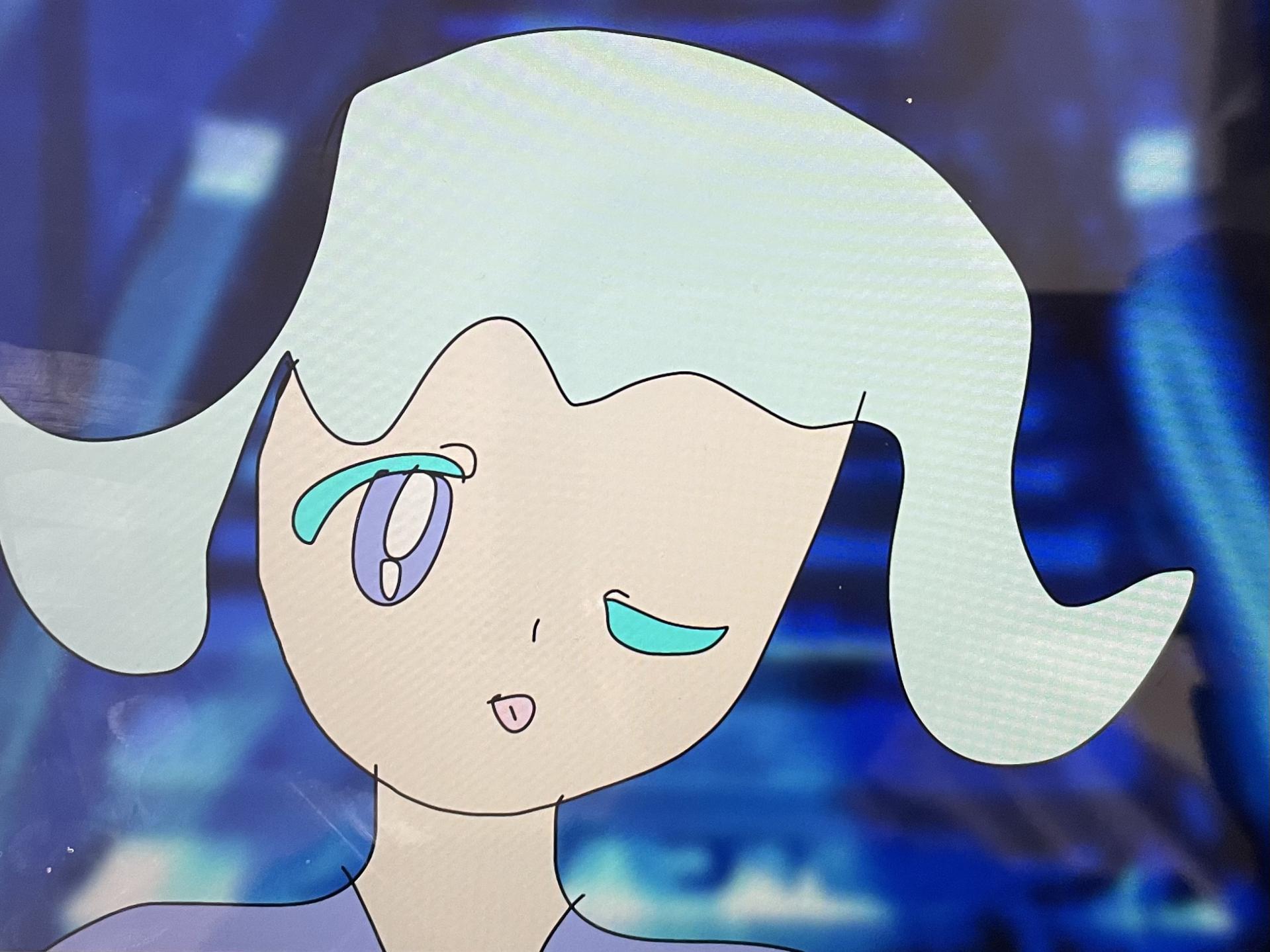江戸時代は、日本の暮らしや文化が大きく変わった時代です。 この記事では、江戸時代の人々の暮らしや文化の特徴を振り返ります。日本の歴史や今も残る伝統について楽しく学んでいきましょう。
この記事をいいねと思ったらクリック!
江戸時代ってどんな時代だった?

江戸時代は日本の歴史において重要な期間であり、多くの変化と発展がありました。
・江戸時代っていつのこと?
江戸時代は江戸幕府という政府が日本をおさめていた、1603年から1867年までの期間です。
江戸時代の間に、日本はとても発展しました。政治や経済、文化が大きく進歩して、今の日本の社会のもとがつくられた時代でもあります。
江戸時代の発明や文化は今でも日本の伝統として大切にされています。
・江戸時代は徳川家康が開いた
江戸時代の始まりは徳川家康が1603年に江戸幕府を作ったことがきっかけです。
戦国時代が終わり、豊臣秀吉が亡くなったあと、徳川家康は日本の政治のトップになりました。そして、1603年に「征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)」という、一番えらい武士のリーダーになり、江戸(今の東京)を中心に新しい政府を作りました。これが江戸幕府です。
・江戸時代はおよそ260年も続いた!
江戸時代はおよそ260年もの長いあいだ続きました。これほど長く、戦国時代のような大きな戦争がない平和な時代が続いたのは、徳川幕府のしっかりしたルールやしくみがあったからです。
徳川幕府は身分をはっきりと分ける制度を作りました。例えば、武士、農民など、それぞれの役わりが決められました。また、幕府は「鎖国(さこく)」というルールを作り、外国との交流を少なくすることで、戦争が起こることを防いでいました。
江戸時代ってどんな暮らし?

江戸時代の暮らしは、今の日本とちがうところがたくさんあります。江戸時代の生活や食事、遊びについて見てみましょう。
・裏長屋に住んでいる人が多かった
江戸時代の都市部、特に江戸では、多くの人が「裏長屋(うらながや)」という家に住んでいました。
裏長屋とは木でできた簡単な作りの家で、細い道の両側にたくさんの家がならんでつながっている住まいのことです。ひとつひとつの家は小さく、玄関と部屋はつながっていて、ふすまやカーテンがないため、他の家ととても近い距離に感じられたでしょう。
裏長屋に住む人びとは江戸の町人や商人、職人などさまざまな仕事をする人が多く、彼らのおかげで、江戸の町はとてもにぎやかになったのです。
・江戸時代中期には1日3食が定着した
実は、江戸時代のはじめのころは朝と夕方の1日2回の食事が普通でした。しかし、江戸時代の中ごろになると、1日3回の食事をとる習慣が広まったとされています。
その理由は、農業の技術が発展して、お米や食べ物がたくさん作れるようになったからです。食べるものが増えたことで、朝・昼・夜の3回に分けて食べることができるようになりました。
食事の内容は、朝にはお米やお粥(かゆ)、昼食にはおにぎり、夕食には魚や野菜を含むおかずも食べるようになったそうです。そして、江戸時代には外食文化も発展していき、お店でごはんを食べることもできるようになりました。
・江戸時代中期からは屋台が広がった
江戸時代の中ごろになると、屋台(やたい)がたくさん広がり、町の人たちの楽しみのひとつになりました。町がどんどん大きくなり、住人がふえたことで、手軽にごはんを食べたい人が多くなり、屋台がたくさんできたのです。
屋台では、今でも人気のある寿司やそば、おでんなどを手軽に楽しむことができました。また、夏祭りやイベントのときには、今と同じように食べ物の屋台だけでなくおもちゃを売る屋台もあったそうです。
屋台は江戸時代中期において、町人たちの暮らしを支える大切な場所だったのです。
江戸時代の文化には何がある?

江戸時代は、日本の歴史の中でも特に文化が花開いた時代として知られています。江戸時代に生まれた芸術や文学は、今の日本にも影響を与えています。
・歌舞伎や浮世絵
歌舞伎や浮世絵は、江戸時代を代表するとても人気のある芸術文化です。
歌舞伎は庶民の文化として多くの人に愛されたお芝居です。中でも「見得を切る」という、決めポーズをするしぐさがかっこいいと人気になりました。
浮世絵は江戸の町の人々の暮らしや、美しい風景をえがいた絵で、多くの人々の心を掴みました。
特に有名な浮世絵は葛飾北斎(かつしか ほくさい)の「富嶽三十六景(ふがく さんじゅうろっけい)」です。この浮世絵は富士山をいろいろな場所から描いた 有名な作品です。
歌舞伎や浮世絵は今でも国内外のたくさんの人に愛されています。
・俳句や川柳
江戸時代には、俳句(はいく)や川柳(せんりゅう)という短い言葉で表現する文学が発展しました。
俳句は、シンプルな言葉の中に、自然、季節の美しさをこめる短い詩です。江戸時代の有名な句には松尾芭蕉(まつおばしょう)の「古池や蛙飛びこむ水の音」という作品があります。この俳句は、池にカエルが飛び込んだ水の音が聞こえるほどの静けさを感じられる作品です。
一方、川柳はおもしろい言葉や世の中のことを面白可笑しく表現する短い詩が多くありました。川柳は今でも「サラリーマン川柳」などの形で、くすっと笑える短い詩として、人気があります。
江戸時代はどうして終わったの?

江戸時代は長く続いた安定した時代でしたが、最終的には様々な要因が重なり幕を閉じました。その中心的な出来事について見てみましょう。
・ペリーが日本に来たことがきっかけになった
1853年、ペリーが率いるアメリカの船「黒船(くろふね)」が日本にやってきたことで江戸時代の政治の状況が大きく変わることになります。
それまでの日本は、鎖国(さこく)というルールで外国との交流をほとんどしていませんでした。しかし、ペリーが日本に開国を求めたことで鎖国の体制が崩れ、幕府の信頼が失われることになりました。
1854年に日本はアメリカと「日米和親条約(にちべい わしんじょうやく)」という約束をかわし、日本は外国と交流することになります。
この出来事によって、日本の人たちは「外国と仲よくするのはよいこと」と考える人もいれば、「日本は鎖国を続けるべきだ」と考える人もいて、対立してしまったのです。
・大政奉還(たいせいほうかん)が行われた
大政奉還(たいせいほうかん)江戸時代が終わる大きなきっかけになった出来事です。
江戸時代の終わりごろ、ペリーの来航によって幕府の力が弱くなり、人々の間では「新しい政治をしよう!」という声が大きくなりました。この時代に幕府をおさめていた徳川慶喜(とくがわ よしのぶ)は争いを防ぐ ために政権を朝廷に返すことを決めました。
これが1867年に起きた、大政奉還です。大政奉還が行われたことで、政治の中心は天皇のもとへ戻り、日本は新たな時代である「明治時代」へと移行します。長く続いた幕府の時代が終わり、日本は近代国家へと進んでいくことになったのです。
江戸時代の意義と現代への影響
江戸時代は、日本の歴史の中でもとても大切な時代でした。戦国時代が終わり、約260年ものあいだ平和が続いたことで、人々の暮らしや文化が大きく発展しました。今の日本にも、江戸時代の名残がたくさんあります。
たとえば、江戸時代に広まった屋台の文化は、今の「屋台グルメ」につながっていますし、歌舞伎や浮世絵、俳句といった文化も今なお大切にされ、国内外の人々に愛されています。
「昔の人はどんな暮らしをしていたのだろう?」「今と何が違うのかな?」と思ったら、博物館で江戸時代の道具を見たり、歴史の本を読んだり、江戸時代の街並みを再現した施設を訪れたりするのも面白いですよ。実際に見たり体験したりすると、教科書ではわからなかった江戸の人々の知恵や工夫に気づくことができるかもしれません。
歴史を学ぶことは、ただ昔のことを知るだけではなく、今の暮らしや未来をよりよくするヒントを見つけることにもつながります。江戸時代の人たちが大切にしていたことや工夫を知ることで、今の日本や自分たちの生活を見つめ直すきっかけになるかもしれませんね。