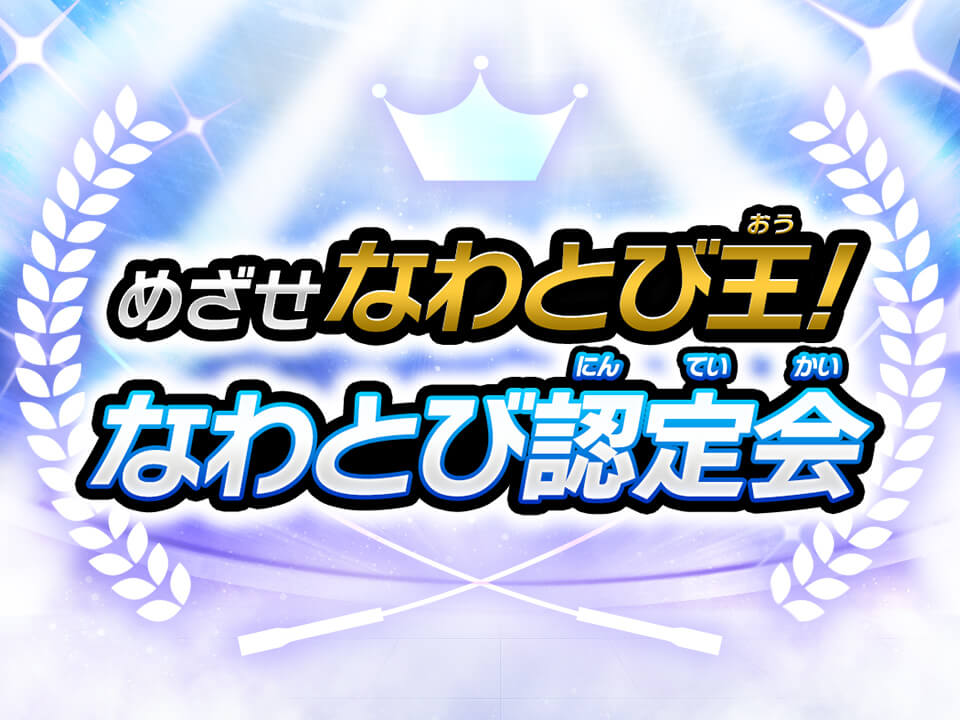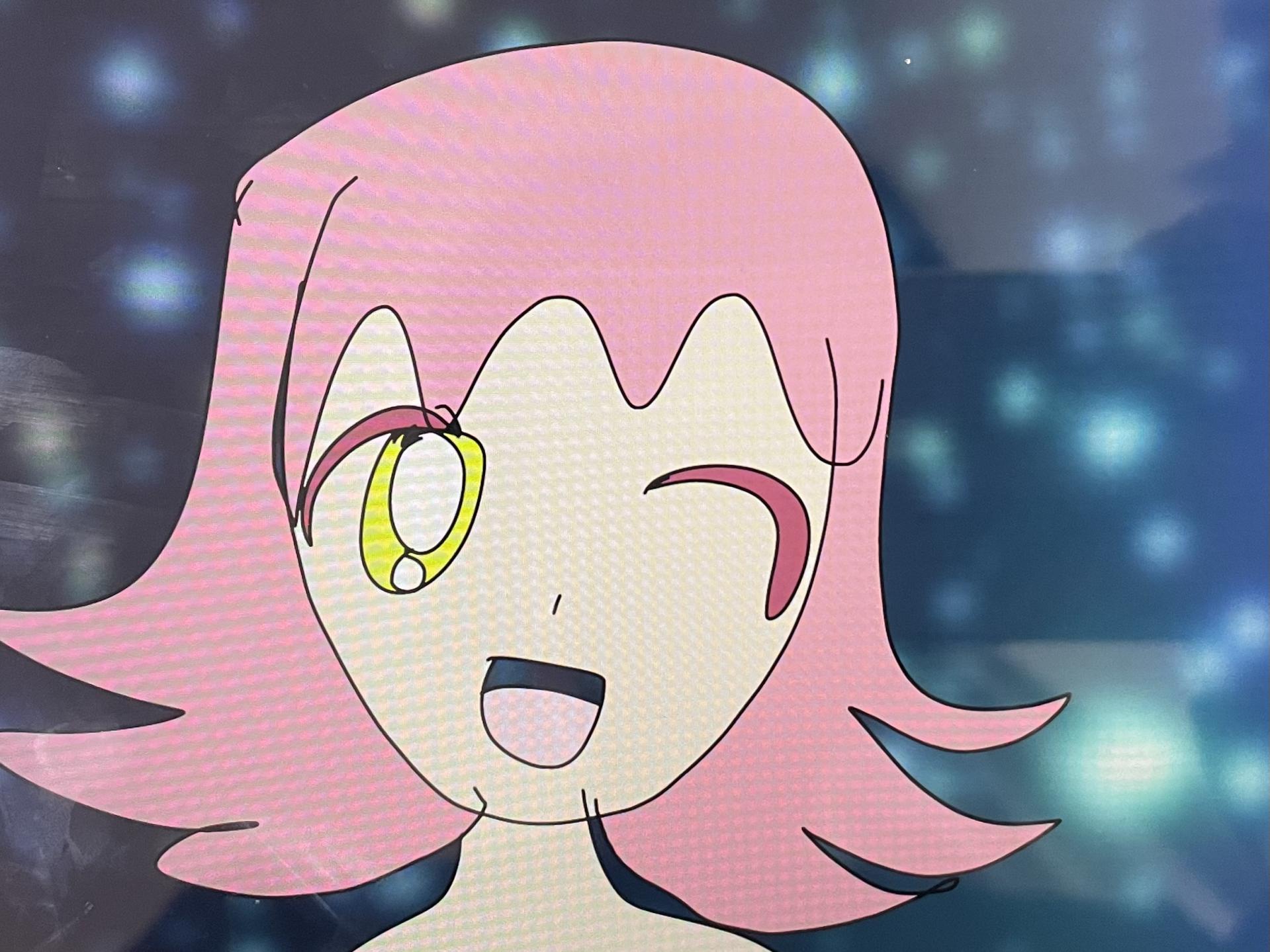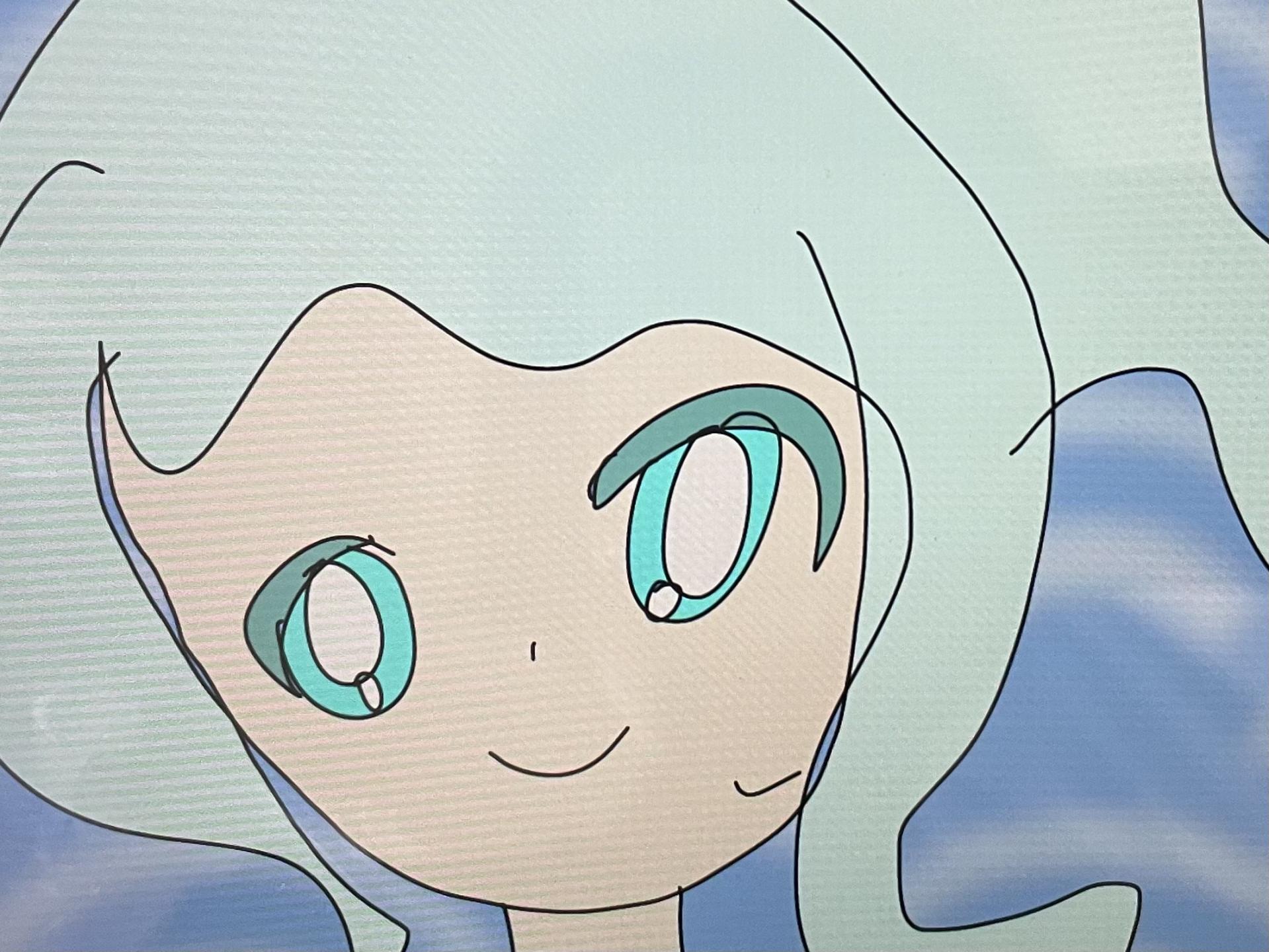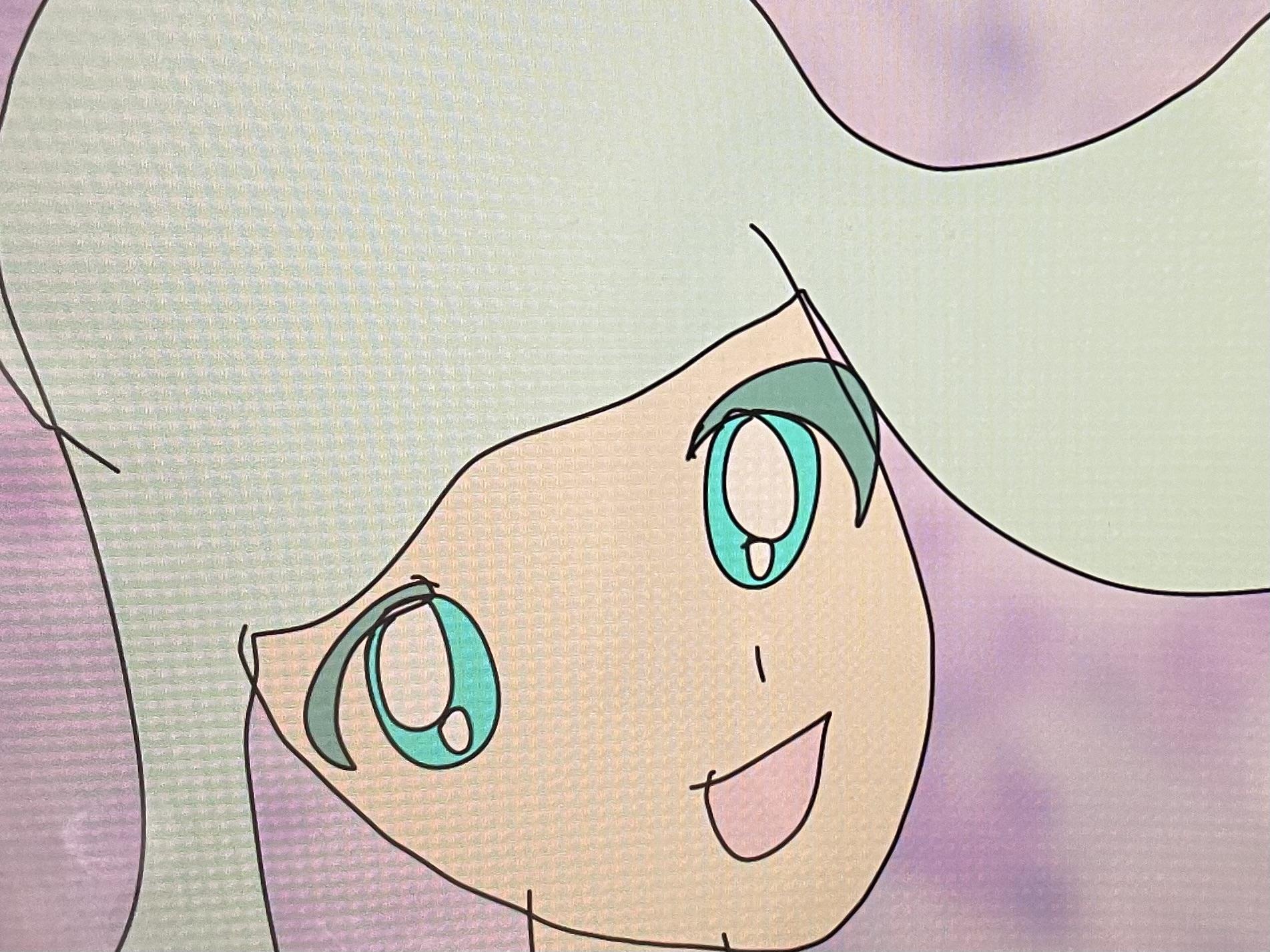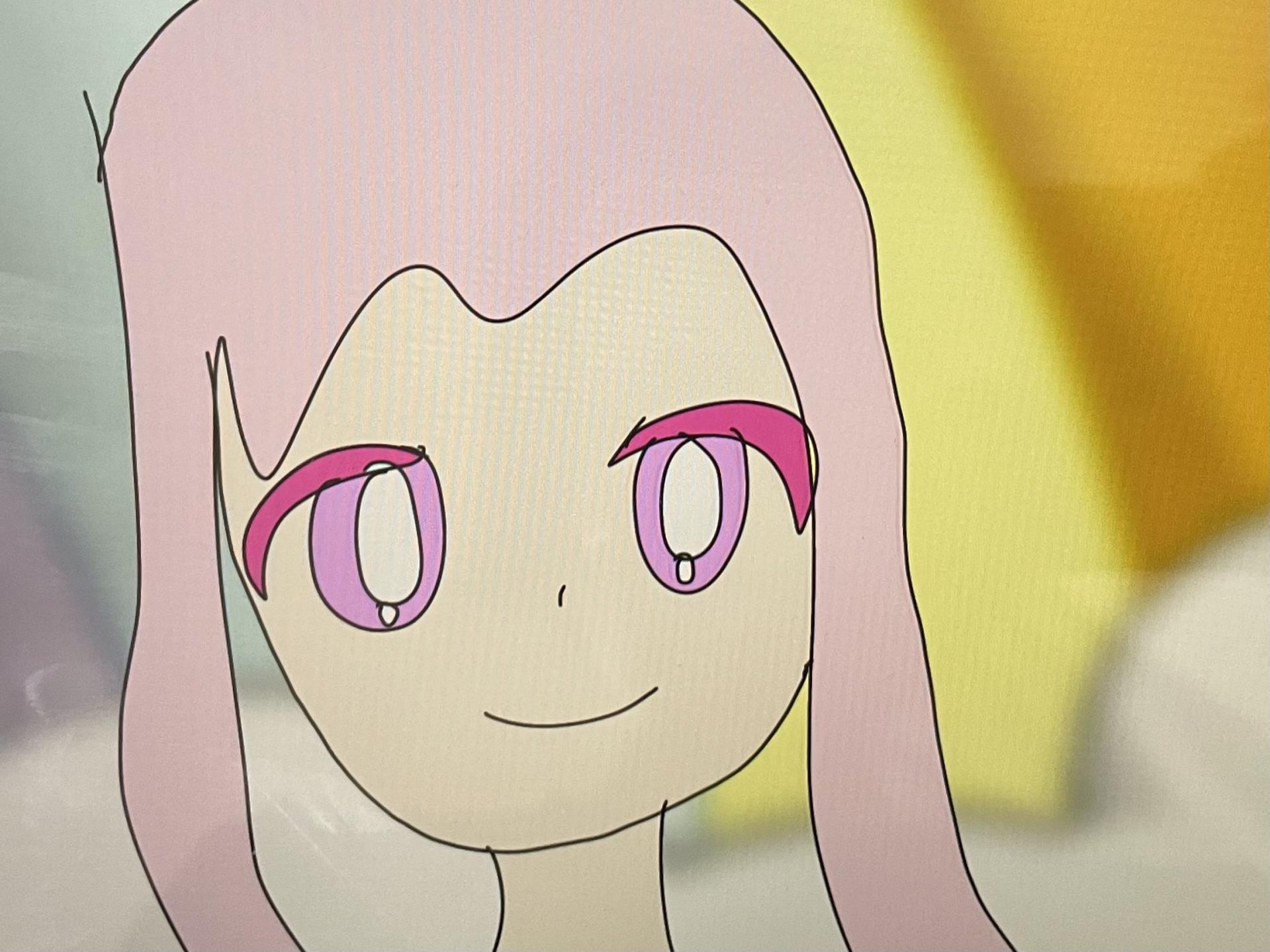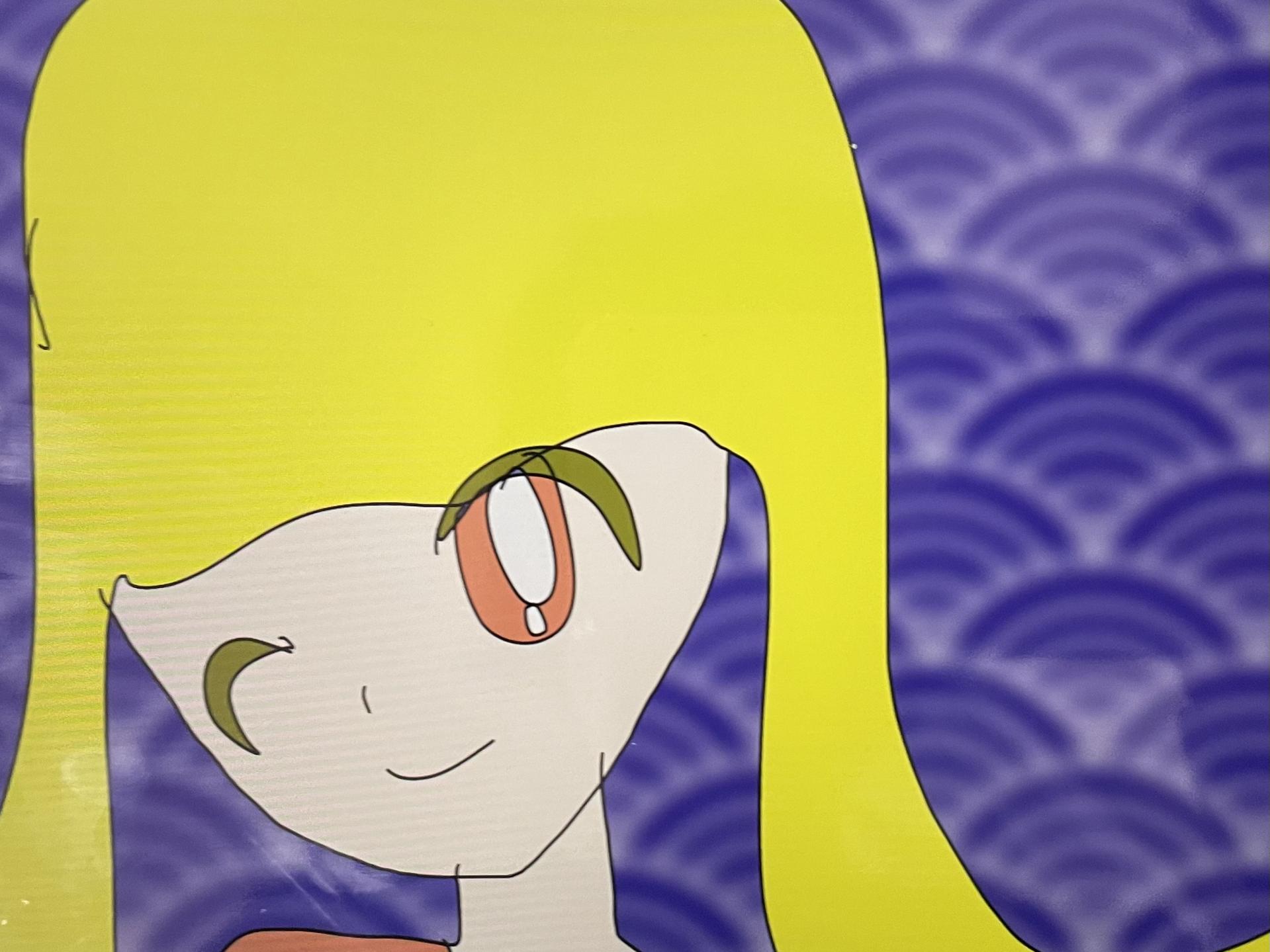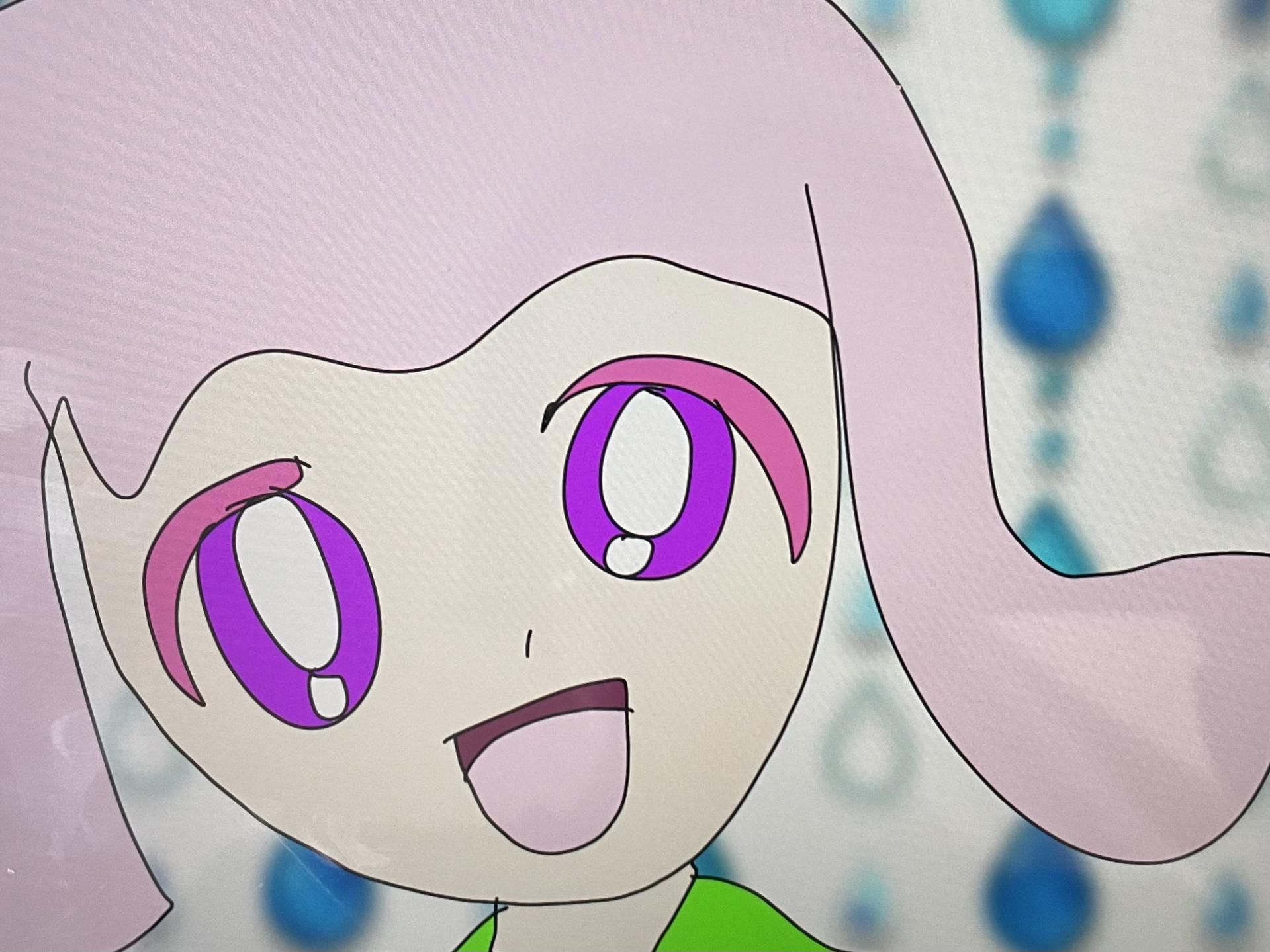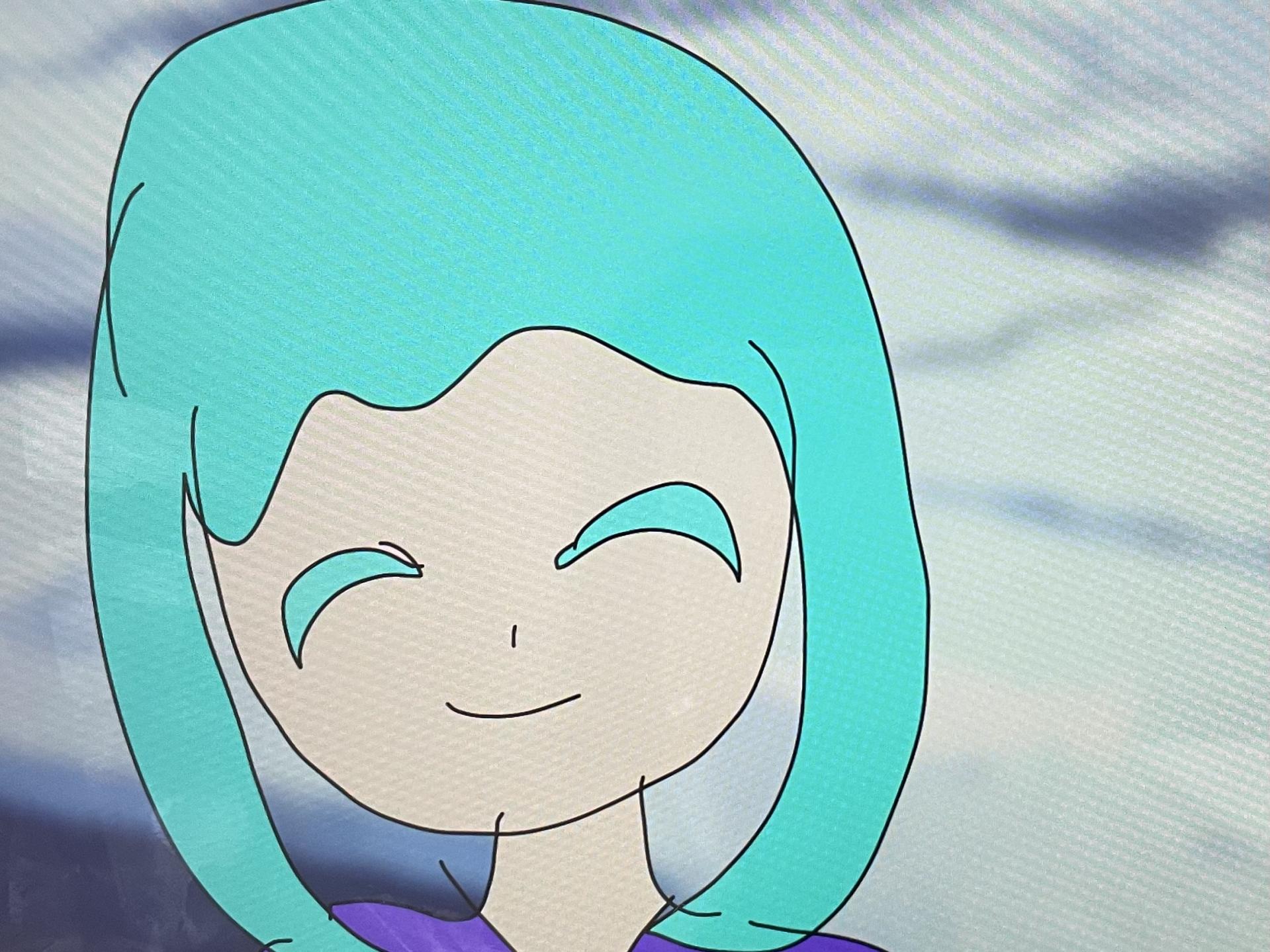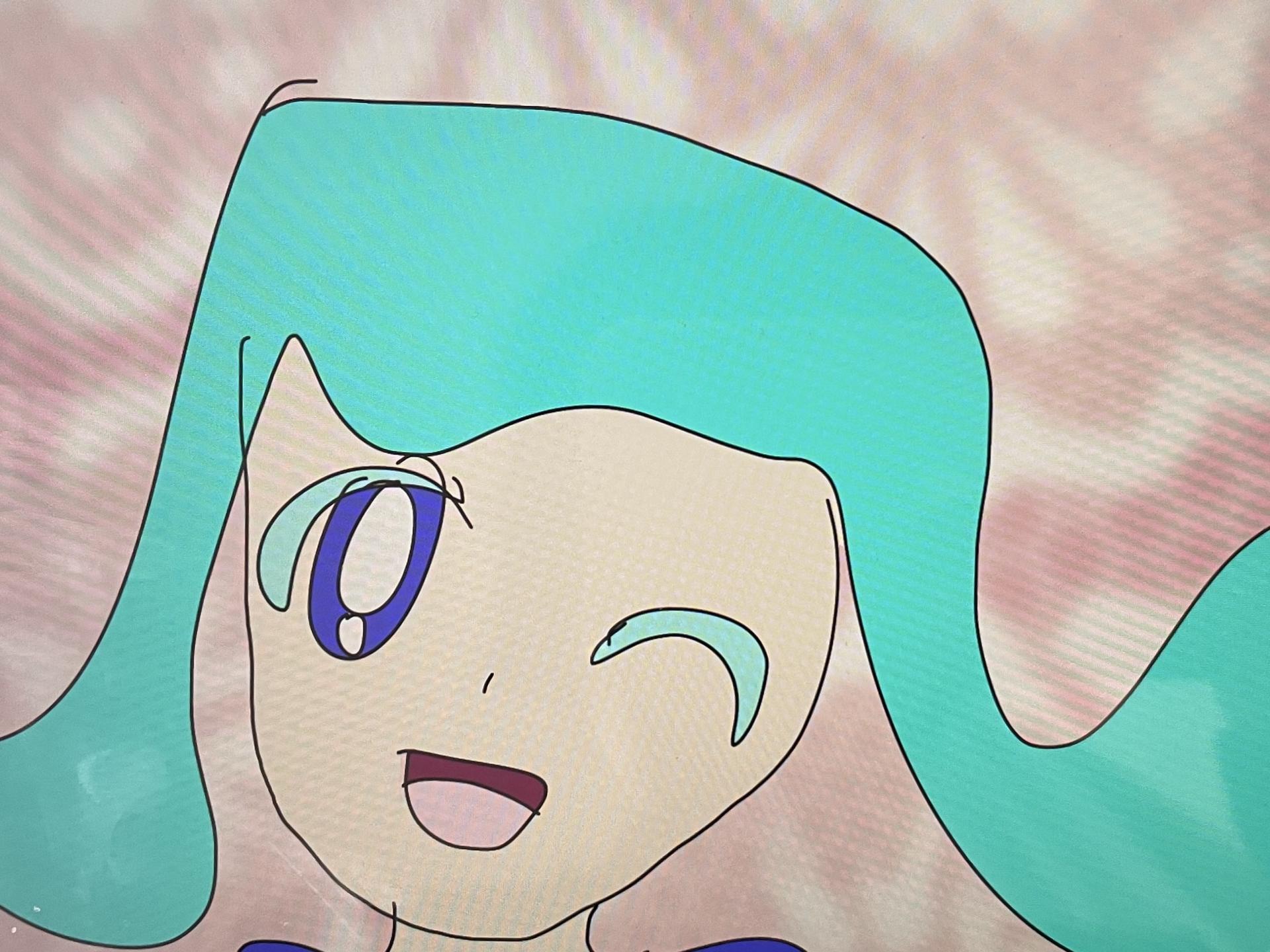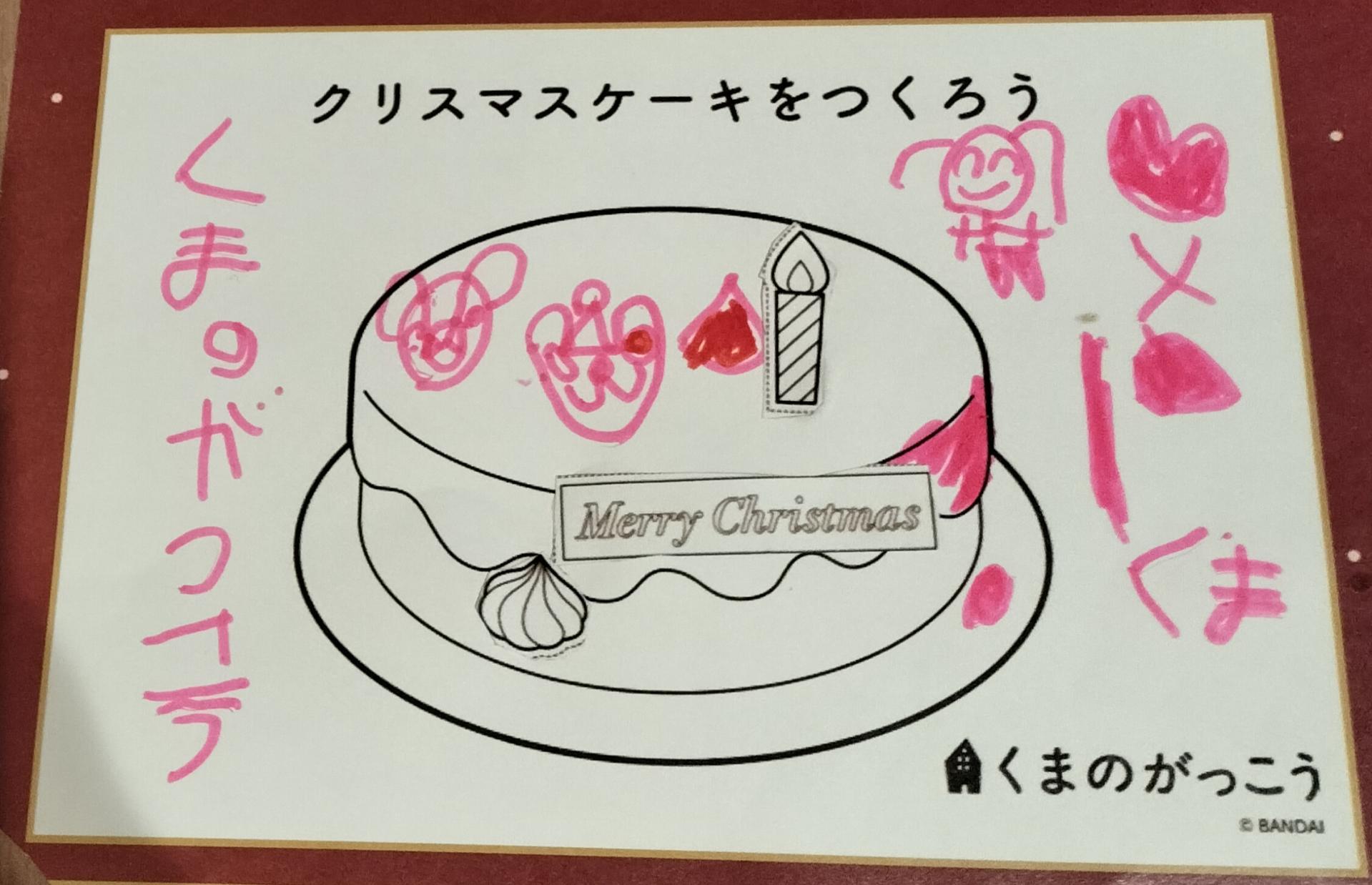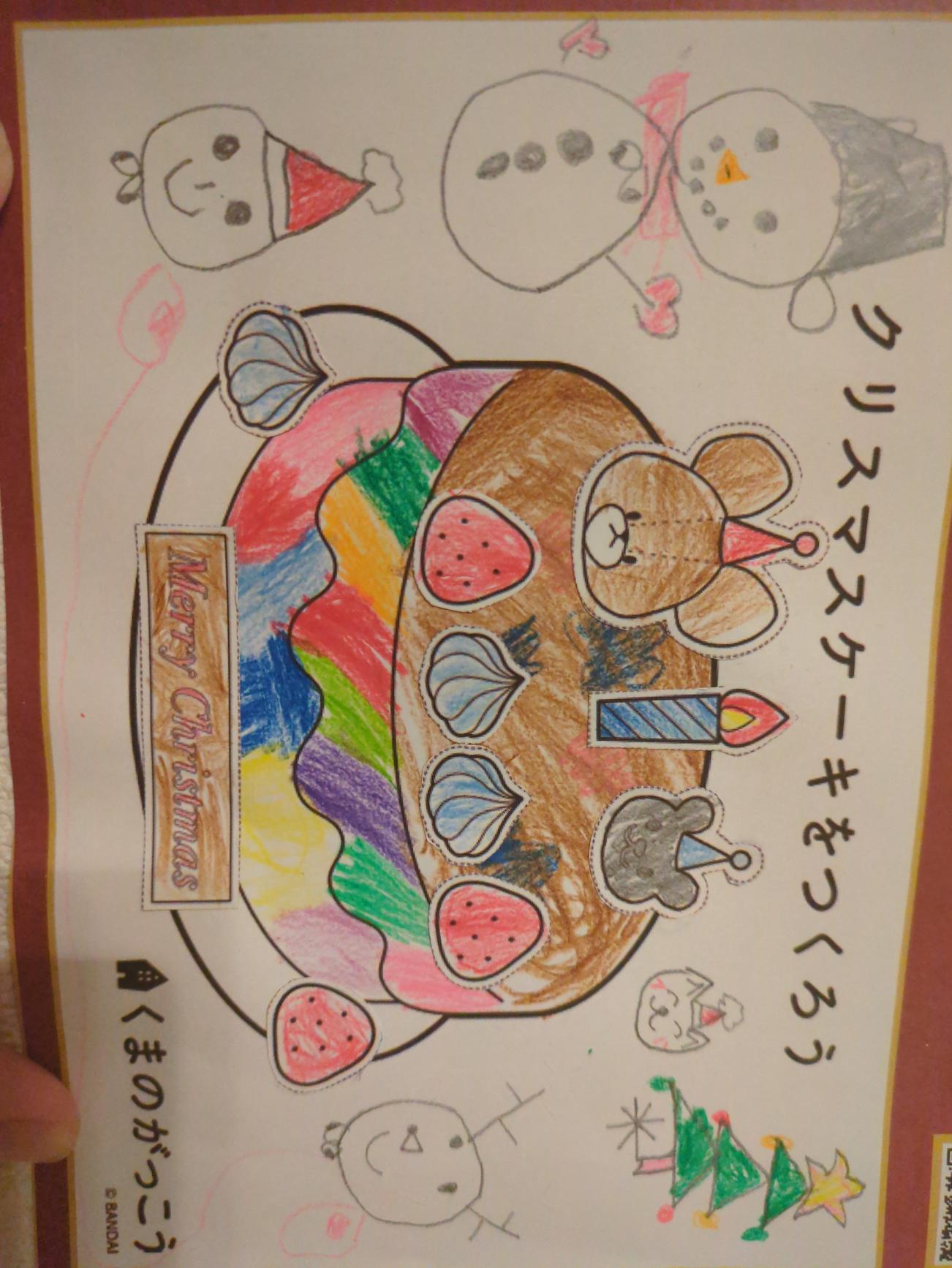納豆は、日本の食卓に昔から親しまれている伝統的な食品です。ねばねばとした食感と独特の香りが特徴で、ごはんのお供として人気があります。では、納豆はいつ、どのようにして生まれたのでしょうか? 昔の人々がどのように納豆を作り、食べていたのかを知ると、普段食べている納豆がもっと身近に感じられるかもしれません。 この記事では、納豆の起源や歴史をひもときながら、昔と今の作り方の違いにつてなどを紹介します。納豆のルーツを知ることで、いつもの食事がちょっと特別に感じられるかもしれませんね。さっそく、一緒に見ていきましょう!
この記事をいいねと思ったらクリック!
納豆の歴史はいつ頃始まった?

納豆は日本の食卓に欠かせない食品ですが、その起源についてははっきりとした記録が残っていません。しかし、古い時代から納豆に似た発酵食品が食べられていたと考えられています。ここでは、納豆の誕生にまつわる3つの説を見ていきましょう。
・【その1】縄文時代の終わりには納豆のようなものが食べられていた?
縄文時代の後半、日本にはすでに発酵食品があったと考えられています。発酵とは、小さな生き物(菌)が食べ物の中で働いて、味や栄養を変えることです。例えば、納豆は納豆菌が大豆を発酵させることで、ねばねばとした食感やうまみが生まれます。
この時代、中国から稲作(いなさく)が伝わり、収穫した稲藁(いなわら)がよく使われるようになりました。そして、日本にはすでに大豆もありました。
ある日、煮た大豆が稲藁に包まれたまま放置されることがあったかもしれません。納豆菌が付いた稲藁によって大豆が偶然発酵して納豆のようなものができた可能性があります。
確かな証拠はありませんが、縄文時代の人々が発酵食品を食べていたことを考えると、納豆に似た食べ物もあったかもしれませんね。
・【その2】聖徳太子が飛鳥時代に発見した?
飛鳥時代、聖徳太子(しょうとくたいし)が納豆を発見した、という伝説があります。
聖徳太子は馬に煮豆をエサとして与えていましたが、ある日余ったので、稲藁で包んで保存していると、煮豆が納豆になっていたそうです。当時は発酵の仕組みが知られていなかったため、これは偶然の発見だったのかもしれません。
この話はあくまで伝説ですが、昔から納豆のような食べ物があったことを想像させるおもしろい説ですね。
・【その3】平安時代の武将が兵士たちの食料にした?
平安時代、源義家(みなもとのよしいえ)※1.という武将が戦に向かう途中、納豆を発見したという話があります。
源義家の軍では、煮た大豆を稲藁に包んで馬の背に載せ、兵士の食料として運んでいました。すると、しばらくして大豆がねばねばになっていたのです。
源義家が食べてみると、おいしくて栄養もあることが分かりました。そこで、兵士たちの食料として取り入れ、その後、農民の間にも広まっていったといわれています。
この話が本当かどうかは分かりませんが、納豆が人々の暮らしに根付いていったきっかけのひとつかもしれませんね。
※1.八幡太郎義家(はちまんたろうよしいえ)とも呼ばれる
納豆の作り方は昔と今で違うの?

納豆は日本の伝統的な発酵食品ですが、昔と今では作り方が大きく異なります。昔は稲藁(いなわら)を使い自然の力で発酵させていましたが、今では主に工場で生産されています。では、それぞれの作り方を詳しく見ていきましょう。
・昔はわらに包んで作られていた
昔の納豆は、煮た大豆を稲藁に包んで発酵させて作っていました。稲藁には納豆菌(なっとうきん)が自然についており、大豆を包んでおくと菌が働き、納豆ができあがります。
この方法は特に冬に行われ、保存食としても重宝されていました。気温や湿度に左右されやすいため、毎回同じ品質にするのは難しかったものの、家庭でも手軽に作ることができました。
現在でも、伝統的な製法を守る生産者がわら納豆を作り続けています。稲藁で発酵させた納豆は、独特の香りや風味があり、昔ながらの味を楽しみたい人に人気があります。
・今は工場で作られている
現在、多くの納豆は工場で温度や湿度を管理しながら作られています。主な手順は以下の通りです。
1.大豆を蒸す:高圧釜でやわらかくする
2.納豆菌を加える:培養された納豆菌を均等にまぶす
3.発酵させる:約40℃の発酵室で管理する
4.冷却・熟成:風味を整え、出荷準備をする
この方法により、安定した品質の納豆を、手頃な価格で手に入れられるようになりました。
納豆に含まれている成分は?

昔から日本の食卓に親しまれてきた納豆ですが、その魅力は独特の食感や風味だけではありません。納豆には、体にうれしい栄養がたくさん含まれています。
では、納豆にはどのような栄養素があり、どんな働きをするのでしょうか?
・納豆にはさまざまな栄養素が含まれている!
納豆には、体に必要な栄養素が豊富に含まれています。これは、発酵の過程で栄養価がさらに高まるためです。納豆に含まれる主な栄養素は、次のとおりです。
*タンパク質:筋肉や皮膚を作る大切な成分
*ビタミンK2:骨を丈夫にし、血液の流れを助ける
*ビタミンB2:エネルギーを作るのを助ける
*マグネシウム・亜鉛:体の調子を整え、免疫力を高める
*カルシウム:骨や歯を強くする
*食物繊維:腸の調子を整え、便秘を防ぐ
特にビタミンK2は、カルシウムの吸収を助け、骨を健康に保つ働きがあります。納豆を食べることで、成長期の子どもや骨を丈夫にしたい人にとってもうれしい効果が期待できるのです。
・特に注目されているのは「ナットウキナーゼ!」
納豆に含まれる栄養素の中でも、特に注目されているのが「ナットウキナーゼ」です。これは、納豆が発酵する過程で生まれる酵素(こうそ)で、血液の流れを良くする働きがあります。
血液には、傷をふさいだりするために血栓(けっせん)という固まりができます。しかし、血栓が増えすぎると血管が詰まり、心臓病や脳卒中の原因になることがあります。ナットウキナーゼには、こうした血栓を溶かす働きがあるため、健康な血流を保つ手助けをしてくれるのです。
ただし、ナットウキナーゼは熱に弱いため、加熱しすぎるとその働きが弱まってしまいます。納豆を食べるときは、できるだけそのまま食べるのがよいでしょう。
日本の納豆の種類は?

昔納豆にはいくつかの種類があり、それぞれ味や食感、作り方が違います。どんな納豆があるのかを知ると、食べ方の楽しみも広がりますね。ここでは、「糸引き納豆」と「塩辛納豆」について紹介します。
・ネバネバした糸を引く「糸引き納豆」
糸引き納豆は、日本で最も一般的な納豆です。スーパーで売られている納豆の多くがこれにあたります。ご飯と相性がよく、混ぜるとネバネバと糸を引くのが特徴です。
納豆が糸を引くのは、「ポリグルタミン酸」という成分が発酵の過程で生まれるためです。この成分によって、納豆ならではの粘りと食感が生まれます。
食べやすく、さまざまな料理にも使いやすいことから、多くの人に親しまれています。
・乾燥させた糸を引かない「塩辛納豆」
塩辛納豆は、糸を引かず、粘り気のない納豆です。これは、作り方が違うためです。
煮た大豆に塩を加えて発酵させたあと、しっかり乾燥させることで、長期間保存できるようになっています。そのため、昔から旅の携帯食や保存食として利用されてきました。
味は名前の通り塩気が強く、糸引き納豆とは違った風味を楽しめます。そのまま食べるだけでなく、お茶漬けやお酒のおつまみにも向いています。
食感や味が異なるため、いつもと違う納豆を試したい人におすすめです。
納豆の歴史には謎がいっぱい!
納豆の歴史はとても古く、その起源にはさまざまな説があります。縄文時代から平安時代にかけて、納豆に似た食品が食べられていた可能性があり、時代とともに作り方も変化してきました。今では、工場で安定した品質の納豆が作られ、いつでも手軽に食べられるようになっています。
また、納豆は栄養価の高さでも注目されています。特に「ナットウキナーゼ」は血液の流れを良くする働きがあることで知られ、健康食品としても関心を集めています。
この記事を読んで、納豆について新しい発見がありましたか?いつも食べている納豆も、歴史や栄養を知ると、ちょっと特別に感じられるかもしれませんね。
次の食事で納豆を食べるとき、ぜひ「こんな歴史があるのか」と思いながら味わってみてください。そして、家族や友だちにも納豆の豆知識を話してみてはいかがでしょうか?